新収 開山無相大師六五〇年遠諱記念「妙心寺」 ― 2009/02/02 23:49
東京国立博物館・京都国立博物館・読売新聞社、
『開山無相大師六五〇年遠諱記念「妙心寺」』(展覧会図録)、読売新聞社、2009年。
観覧した時は比較的すいていた。相変わらず禅の用語は難しいと思うが、意味がわかれば、味わい深い。わかりやすい展示物をあげるとすれば、豊臣棄丸(鶴松)の子供用鎧だろうか。観覧した時、年配の女性数人がそのケースを囲んでいた。豪華な図録が2500円は安い。
日本のものをみなれた我々は、普段見慣れない石造りの建物や西欧的な豪華さ明晰さ、中国の遠大な歴史に圧倒され、魅了される。それはそれで実際、それだけの価値がある。しかしここにあるものも同様に驚くべき存在なのだとあらためて認識させられた。
外国史を専攻したせいか、最近、それがきわだって大きく感じられるようになった。
期待していた通り、南化玄興の頂相もあった。個人的には南化玄興といえば直江兼続を連想するようになってしまった。ここではその関係は紹介されていないがまあそれはそれでよい。ブームに乗る必要はない。ただ雪深い中越に生まれた彼がこの荘厳さを目にしたとき、何を思ったか、それが十分に感じられる気がした。
そうだ 京都、行こう、そう思わせる展示だった。
『開山無相大師六五〇年遠諱記念「妙心寺」』(展覧会図録)、読売新聞社、2009年。
観覧した時は比較的すいていた。相変わらず禅の用語は難しいと思うが、意味がわかれば、味わい深い。わかりやすい展示物をあげるとすれば、豊臣棄丸(鶴松)の子供用鎧だろうか。観覧した時、年配の女性数人がそのケースを囲んでいた。豪華な図録が2500円は安い。
日本のものをみなれた我々は、普段見慣れない石造りの建物や西欧的な豪華さ明晰さ、中国の遠大な歴史に圧倒され、魅了される。それはそれで実際、それだけの価値がある。しかしここにあるものも同様に驚くべき存在なのだとあらためて認識させられた。
外国史を専攻したせいか、最近、それがきわだって大きく感じられるようになった。
期待していた通り、南化玄興の頂相もあった。個人的には南化玄興といえば直江兼続を連想するようになってしまった。ここではその関係は紹介されていないがまあそれはそれでよい。ブームに乗る必要はない。ただ雪深い中越に生まれた彼がこの荘厳さを目にしたとき、何を思ったか、それが十分に感じられる気がした。
そうだ 京都、行こう、そう思わせる展示だった。
新収 『史学雑誌』第118編第1号 ― 2009/02/10 02:03
史学会『史学雑誌』第118編第1号、2009年1月
岡部毅史、梁簡文帝立太子前夜-南朝皇太子の歴史的位置に関する一考察
桃木至朗、逆風のなかの東洋史学
シャルロッテ・フォン・ヴェアシェア、日本古代における五穀と年中行事
丸ごと興味深い内容だった。最近南朝の論文が目立つ。
今まで北朝の方が出土資料(特に墓誌)が多かったせいもあるだろうが、最近は南朝にも出土資料が増えているからそうしたところから成果も出てくるに違いない(どうも身近で発表される気配が)。「穀」といえば中林さんからもらった論文をおもいだした。
「大学を含む学術・教育界では、世界イコール欧米という「偏西風」が今なお強く吹いている。」(桃木先生コラム)
逆に欧米分野の教員は「これからはアジアの時代ですね」などといってたりするのだが、・・・数字で見れば実際はコラムのとおりであろう。
要するにできれば役に立つものを、またどうせ時間をつかうならあこがれの分野を選択するのだろう。ヨーロッパにあこがれてもアジアにあこがれる人は少ないということか。また表面的に「役に立つ」ものを選ぶ傾向が強まっているので、古典・教養からはますます学生が離れていくことになる。
そういう状況で、「研究」という金看板を前にあげると学生はどんどん、ひいていく。そもそも職業としての研究者になれる確率はものすごく低くなった。大学で学んだ教養を日常の生活や体験として何に活かせるのか、どうしたらその意味を感じてもらえるのか、それが肝心なのだろう。 そもそも自分の今に役立たない(楽しくない)ことはたしかにだれもやろうとしないのである。(自分がそうだ)。
岡部毅史、梁簡文帝立太子前夜-南朝皇太子の歴史的位置に関する一考察
桃木至朗、逆風のなかの東洋史学
シャルロッテ・フォン・ヴェアシェア、日本古代における五穀と年中行事
丸ごと興味深い内容だった。最近南朝の論文が目立つ。
今まで北朝の方が出土資料(特に墓誌)が多かったせいもあるだろうが、最近は南朝にも出土資料が増えているからそうしたところから成果も出てくるに違いない(どうも身近で発表される気配が)。「穀」といえば中林さんからもらった論文をおもいだした。
「大学を含む学術・教育界では、世界イコール欧米という「偏西風」が今なお強く吹いている。」(桃木先生コラム)
逆に欧米分野の教員は「これからはアジアの時代ですね」などといってたりするのだが、・・・数字で見れば実際はコラムのとおりであろう。
要するにできれば役に立つものを、またどうせ時間をつかうならあこがれの分野を選択するのだろう。ヨーロッパにあこがれてもアジアにあこがれる人は少ないということか。また表面的に「役に立つ」ものを選ぶ傾向が強まっているので、古典・教養からはますます学生が離れていくことになる。
そういう状況で、「研究」という金看板を前にあげると学生はどんどん、ひいていく。そもそも職業としての研究者になれる確率はものすごく低くなった。大学で学んだ教養を日常の生活や体験として何に活かせるのか、どうしたらその意味を感じてもらえるのか、それが肝心なのだろう。 そもそも自分の今に役立たない(楽しくない)ことはたしかにだれもやろうとしないのである。(自分がそうだ)。
新収 『史滴』第30号 ― 2009/02/10 02:48
早稲田大学東洋史懇話会『史滴』第30号、2008年12月。
特集「フィールド歴史学」
近藤一成、「フィールド歴史学」の提案
近藤先生の巻頭論文にも次のような一文がある。
「近年、アジア史学とりわけ東アジア史を専攻する学生が少なくなっている」「この十年ほどの落ち込みは何か底が抜けたという感じである」
この他、戦国~近現代モンゴル、朝鮮半島、18世紀西アジアまで14本の論文・レポートが並ぶ。こんなに厚くて(総293頁)多彩な内容の東洋史の雑誌は近年希有だろう。専攻者数は「落ち込」んではいるが、数年前に院生になった多くの人たちが執筆者や編集者として、これを支えているわけだ。魏晋南北朝隋唐関連でも面白い論文がおおい。以下に一部を紹介した。
森和、「日書」と中国古代史研究ー時称と時制の問題を例に
吉田愛、『花郎世紀』の基礎的研究ー世系・血縁関係記事の分析を中心に
飯山知保、モンゴル時代華北における系譜伝承と碑刻史料
ソグド人漢文墓誌訳注(5) 固原出土「史索巌墓誌(唐・顕慶三年)」
佐野理恵子、『荊楚歳時記』成立の背景をめぐって-魏晋南北朝時代における民間習俗の禁止事例を中心にー
『花郎世紀』は8世紀朝鮮半島の史料であるが、その写本は近年発見されたもので、いまだ真偽がさだかではないとのことである。そのテキストを仔細に分析し、特徴を論じている。
特集「フィールド歴史学」
近藤一成、「フィールド歴史学」の提案
近藤先生の巻頭論文にも次のような一文がある。
「近年、アジア史学とりわけ東アジア史を専攻する学生が少なくなっている」「この十年ほどの落ち込みは何か底が抜けたという感じである」
この他、戦国~近現代モンゴル、朝鮮半島、18世紀西アジアまで14本の論文・レポートが並ぶ。こんなに厚くて(総293頁)多彩な内容の東洋史の雑誌は近年希有だろう。専攻者数は「落ち込」んではいるが、数年前に院生になった多くの人たちが執筆者や編集者として、これを支えているわけだ。魏晋南北朝隋唐関連でも面白い論文がおおい。以下に一部を紹介した。
森和、「日書」と中国古代史研究ー時称と時制の問題を例に
吉田愛、『花郎世紀』の基礎的研究ー世系・血縁関係記事の分析を中心に
飯山知保、モンゴル時代華北における系譜伝承と碑刻史料
ソグド人漢文墓誌訳注(5) 固原出土「史索巌墓誌(唐・顕慶三年)」
佐野理恵子、『荊楚歳時記』成立の背景をめぐって-魏晋南北朝時代における民間習俗の禁止事例を中心にー
『花郎世紀』は8世紀朝鮮半島の史料であるが、その写本は近年発見されたもので、いまだ真偽がさだかではないとのことである。そのテキストを仔細に分析し、特徴を論じている。
拝受 契嵩の護法思想 ほか ― 2009/02/12 12:24
中西久味、契嵩の護法思想、『日本中国学会報』第60集、2008年10月。
中西久味、柳田聖山という先生、『柳田聖山先生追悼文集』、2008年11月。
中西先生からいただいた。ありがとうございました。契嵩は十一世紀の人。
前者の中で米沢図書館蔵本『鐔津文集』にふれられている。そこに示されているとおり、米沢本『鐔津文集』は至元十九年(1282)の版本である。『鐔津文集』には「米澤蔵書」印が捺されている。したがって「米澤蔵書」印が捺されている書籍として、光宗中(1194~1200)補刊『千金要方』についで古いのは『鐔津文集』であり、『韻府群玉』(米沢本は元統二年(1334))はそれにつぐ。
拙稿「「米澤蔵書」からみた江戸期における藩校蔵書の形成」では『千金要方』についで古いものを『韻府群玉』と記述したが、この点は修正しなくてはならない。米沢本『鐔津文集』が至元十九年の版本であることは『米沢善本の研究と解題』(1958)以前の米沢図書館『珍書目録』(1911)にすでにあきらかである。なお、米沢本『鐔津文集』、『韻府群玉』ともに五山・林下の寺院由来とみられる。
ついでに拙稿では「米澤蔵書」印が捺された下限とみられるものを寛文九年(1669)の『読耕林先生文集』としているが、脱稿後まもなくの調査でさらに年代が下る書籍があることなどが判明している(この点は『米沢善本の研究と解題』ではわからない)。このように「米澤蔵書」印が捺された書籍の刊年については上下限ともに記述を修正する必要がある。それでもおおかたの論旨には影響はないようだが、そのままにしておくわけにもいかないので調査、報告をしなおす必要があると思っていたところだった。
当面、まとまった文章が書けそうにないので、中西先生のお仕事にかこつけてここに付記させていただく。
中西久味、柳田聖山という先生、『柳田聖山先生追悼文集』、2008年11月。
中西先生からいただいた。ありがとうございました。契嵩は十一世紀の人。
前者の中で米沢図書館蔵本『鐔津文集』にふれられている。そこに示されているとおり、米沢本『鐔津文集』は至元十九年(1282)の版本である。『鐔津文集』には「米澤蔵書」印が捺されている。したがって「米澤蔵書」印が捺されている書籍として、光宗中(1194~1200)補刊『千金要方』についで古いのは『鐔津文集』であり、『韻府群玉』(米沢本は元統二年(1334))はそれにつぐ。
拙稿「「米澤蔵書」からみた江戸期における藩校蔵書の形成」では『千金要方』についで古いものを『韻府群玉』と記述したが、この点は修正しなくてはならない。米沢本『鐔津文集』が至元十九年の版本であることは『米沢善本の研究と解題』(1958)以前の米沢図書館『珍書目録』(1911)にすでにあきらかである。なお、米沢本『鐔津文集』、『韻府群玉』ともに五山・林下の寺院由来とみられる。
ついでに拙稿では「米澤蔵書」印が捺された下限とみられるものを寛文九年(1669)の『読耕林先生文集』としているが、脱稿後まもなくの調査でさらに年代が下る書籍があることなどが判明している(この点は『米沢善本の研究と解題』ではわからない)。このように「米澤蔵書」印が捺された書籍の刊年については上下限ともに記述を修正する必要がある。それでもおおかたの論旨には影響はないようだが、そのままにしておくわけにもいかないので調査、報告をしなおす必要があると思っていたところだった。
当面、まとまった文章が書けそうにないので、中西先生のお仕事にかこつけてここに付記させていただく。
またミス ― 2009/02/14 03:20
いやー。新稿にミスが。あとで訂正しますけどね。
まあ、概説や辞書あたりでもよく間違えているんで、最初は見きわめないまま書いてしまったのかもしれないけど、いろんな要素が重なったようだ。なぜそのままにしていたのか不思議なくらいだ。
「銅」じゃなくて「木」だった。メダルではありません。ともかく後日。
まあ、概説や辞書あたりでもよく間違えているんで、最初は見きわめないまま書いてしまったのかもしれないけど、いろんな要素が重なったようだ。なぜそのままにしていたのか不思議なくらいだ。
「銅」じゃなくて「木」だった。メダルではありません。ともかく後日。
新収 敦煌学導論 ― 2009/02/14 17:58
李正宇(著)『敦煌学導論』(李正宇学術文集2)甘粛人民出版社、2008年10月。
第一章 緒論
第二章 莫高窟文物及其流出
第三章 敦煌芸術
第四章 敦煌遺書
第五章 敦煌其他古遺址・遺物
第六章 敦煌学的興起和発展
第七章 敦煌学的材料与敦煌学的体系結構
第八章 敦煌学各分支学科研究概況
第九章 敦煌学的特点及価値意義
第十章 敦煌資料目録・敦煌学研究論著目録及敦煌遺書・敦煌壁画彩塑的刊布
第十一章 敦煌学入門
第十二章 敦煌学通常使用的研究方法
第十三章 敦煌学在国外
附載 敦煌文献選講
附載は敦煌文献に釈文と注釈を加えたもの。
田籍、契券、物価、計量、徴納、水利、寺院経済、採礦鑄銭、訓誡、結社、訴訟、社会経済、蓄奴・放良、帰義軍及金山国関係、民族関係、楽舞活動、文学作品、中外科技交流、漢簡と多岐にわたる。ただし、それぞれのジャンル毎に1~5点選んだもので契券だけは13点が選ばれている。
第一章 緒論
第二章 莫高窟文物及其流出
第三章 敦煌芸術
第四章 敦煌遺書
第五章 敦煌其他古遺址・遺物
第六章 敦煌学的興起和発展
第七章 敦煌学的材料与敦煌学的体系結構
第八章 敦煌学各分支学科研究概況
第九章 敦煌学的特点及価値意義
第十章 敦煌資料目録・敦煌学研究論著目録及敦煌遺書・敦煌壁画彩塑的刊布
第十一章 敦煌学入門
第十二章 敦煌学通常使用的研究方法
第十三章 敦煌学在国外
附載 敦煌文献選講
附載は敦煌文献に釈文と注釈を加えたもの。
田籍、契券、物価、計量、徴納、水利、寺院経済、採礦鑄銭、訓誡、結社、訴訟、社会経済、蓄奴・放良、帰義軍及金山国関係、民族関係、楽舞活動、文学作品、中外科技交流、漢簡と多岐にわたる。ただし、それぞれのジャンル毎に1~5点選んだもので契券だけは13点が選ばれている。
新刊 『直江兼続』高志書院刊 ― 2009/02/22 18:23
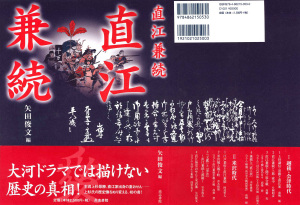
矢田俊文(編)『直江兼続』高志書院、2008年2月。
越後・会津時代
1 上杉謙信・景勝と直江家…………………前嶋 敏
2 直江兼続と一族・家中……………………片桐昭彦
3 直江兼続と関ヶ原合戦……………………高橋 充
〈コラム〉戦と宴の日々………………………高桑 登
〈コラム〉「幻の白河決戦」と上杉氏の城……石田明夫
4 兼続と「直江状」…………………………木村康裕
〈コラム〉解題「長谷堂合戦図屏風」………………高橋 修
米沢時代
1 江戸幕府と直江兼続…………………………阿部哲人
2 米沢城と城下町………………………………青木昭博
〈コラム〉直江兼続が掘った堀……………………高桑 登
3 『文鑑』と『軍法』―直江兼続と漢籍―…………岩本篤志
4 直江後室おせんと米沢藩………………………矢田俊文
〈コラム〉おせんと兼続………… ………………浅倉有子
高志書院 http://www.koshi-s.jp/shinkan/090115_1-shinkan.htm
ジュンク堂 http://www.junkudo.co.jp/detail2.jsp?ID=0011038240
紀伊國屋書店 http://bookweb.kinokuniya.co.jp/htm/4862150535.html
bk-1 http://www.bk1.jp/product/03089557
アマゾン http://www.amazon.co.jp/dp/4862150535
六一書房 http://www.book61.co.jp/book_html/N03268/
-------------------------------------------
私以外は上杉氏関連では定評ある執筆陣である。入門書ではない。どちらかというと論文集に近い。だからかなり歯ごたえがあるはずだ。
しかし、そこまで調べられるだけの史資料が現存し、まだまだ研究者さえ未踏の場所があることに気づいてほしいところである。
日本のおもしろさはまだまだ掘り尽くされていない。そこにはアジアが眠っている。それが僕のパートの役割である。
(補記)直江版『文選』の「活字」について
一般に直江版『文選』は「日本最初の銅活字版」などとされるが、あきらかな誤りである。
拙稿では直江版『文選』が家康の活字印刷などより後になることを提示しつつ、「銅活字本をつくらせたとされる」とした。
しかし、おおかたの学術書は「活字版」とするにとどまり、今回、多くを依拠した川瀬氏の研究にも活字の種類について明記した箇所を確認できない。なお、川瀬氏は直江の片腕であった涸轍が朝鮮半島からもってきた銅活字をもちいて出版をおこなっていた可能性などに言及しているがそれが直江版とはしていない。この時期の活字版で銅活字をもちいた例はきわめて稀とされており、直江版『文選』も木活字による印刷である可能性が高い。
この分野ではまずみるべき『日本古典籍書誌学辞典』は、直江版『文選』を「木活字」と明記していることを付記しておく。
越後・会津時代
1 上杉謙信・景勝と直江家…………………前嶋 敏
2 直江兼続と一族・家中……………………片桐昭彦
3 直江兼続と関ヶ原合戦……………………高橋 充
〈コラム〉戦と宴の日々………………………高桑 登
〈コラム〉「幻の白河決戦」と上杉氏の城……石田明夫
4 兼続と「直江状」…………………………木村康裕
〈コラム〉解題「長谷堂合戦図屏風」………………高橋 修
米沢時代
1 江戸幕府と直江兼続…………………………阿部哲人
2 米沢城と城下町………………………………青木昭博
〈コラム〉直江兼続が掘った堀……………………高桑 登
3 『文鑑』と『軍法』―直江兼続と漢籍―…………岩本篤志
4 直江後室おせんと米沢藩………………………矢田俊文
〈コラム〉おせんと兼続………… ………………浅倉有子
高志書院 http://www.koshi-s.jp/shinkan/090115_1-shinkan.htm
ジュンク堂 http://www.junkudo.co.jp/detail2.jsp?ID=0011038240
紀伊國屋書店 http://bookweb.kinokuniya.co.jp/htm/4862150535.html
bk-1 http://www.bk1.jp/product/03089557
アマゾン http://www.amazon.co.jp/dp/4862150535
六一書房 http://www.book61.co.jp/book_html/N03268/
-------------------------------------------
私以外は上杉氏関連では定評ある執筆陣である。入門書ではない。どちらかというと論文集に近い。だからかなり歯ごたえがあるはずだ。
しかし、そこまで調べられるだけの史資料が現存し、まだまだ研究者さえ未踏の場所があることに気づいてほしいところである。
日本のおもしろさはまだまだ掘り尽くされていない。そこにはアジアが眠っている。それが僕のパートの役割である。
(補記)直江版『文選』の「活字」について
一般に直江版『文選』は「日本最初の銅活字版」などとされるが、あきらかな誤りである。
拙稿では直江版『文選』が家康の活字印刷などより後になることを提示しつつ、「銅活字本をつくらせたとされる」とした。
しかし、おおかたの学術書は「活字版」とするにとどまり、今回、多くを依拠した川瀬氏の研究にも活字の種類について明記した箇所を確認できない。なお、川瀬氏は直江の片腕であった涸轍が朝鮮半島からもってきた銅活字をもちいて出版をおこなっていた可能性などに言及しているがそれが直江版とはしていない。この時期の活字版で銅活字をもちいた例はきわめて稀とされており、直江版『文選』も木活字による印刷である可能性が高い。
この分野ではまずみるべき『日本古典籍書誌学辞典』は、直江版『文選』を「木活字」と明記していることを付記しておく。
新収 北魏職官制度考 ほか ― 2009/02/24 00:57
兪鹿年(著)『北魏職官制度考』社会科学文献出版社、2008年12月。
姚美玲(著)『唐代墓誌詞匯』華東師範大学出版社、2008年10月。
姚美玲(著)『唐代墓誌詞匯』華東師範大学出版社、2008年10月。
新収 『東方学』第117号 ― 2009/02/27 00:12
『東方学』第117号
中田美絵、五臺山文殊信仰と王権
吉永匡史、律令関制度の構造と特質
孟 彦弘(辻正博訳)、唐代の「副過所」及び過所の「副白」「録白案記」辨析
中島楽章、西洋渡航朱印状について
自分が興味を持ったのは以上の論文。
中田論文は「東部ユーラシアの王権イデオロギーの歴史的展開」に新しい知見を加えようとするもの。吉永論文は天聖令とくに関市令をもちいた日唐令の研究。
中田美絵、五臺山文殊信仰と王権
吉永匡史、律令関制度の構造と特質
孟 彦弘(辻正博訳)、唐代の「副過所」及び過所の「副白」「録白案記」辨析
中島楽章、西洋渡航朱印状について
自分が興味を持ったのは以上の論文。
中田論文は「東部ユーラシアの王権イデオロギーの歴史的展開」に新しい知見を加えようとするもの。吉永論文は天聖令とくに関市令をもちいた日唐令の研究。
新収 江戸の食生活 ほか ― 2009/02/27 00:26
原田信男(著)『江戸の食生活』岩波現代文庫、2009年2月。
大津透(著)『道長と宮廷社会』(日本の歴史6)講談社学術文庫、2009年2月。
内容は全く異なるが、これから移動時間にでも熟読してみたいと思っている2冊。
『江戸の食生活』2008年3月15日、読了。これは名著。
大津透(著)『道長と宮廷社会』(日本の歴史6)講談社学術文庫、2009年2月。
内容は全く異なるが、これから移動時間にでも熟読してみたいと思っている2冊。
『江戸の食生活』2008年3月15日、読了。これは名著。