拝受 特別展・上杉家家臣団(図録) ― 2010/10/28 18:38

阿部哲人(編)『特別展・上杉家家臣団』(図録)米沢市上杉博物館、2010年9月。
2010年9月18日から11月23日まで米沢市上杉博物館で開催されている「直江兼続生誕450年 特別展・上杉家家臣団」の図録。フルカラー。今回は漢籍や藩蔵書の類は含まれていないが、家臣団の結びつきがわかる様々な古文書、資料からはいくつの示唆めいたものを得ることができた。
巻末解説「中世越後の小国氏」を執筆した矢田俊文先生からいただいた。ありがとうございました。
米沢市上杉博物館
http://www.denkoku-no-mori.yonezawa.yamagata.jp/uesugi.htm
2010年9月18日から11月23日まで米沢市上杉博物館で開催されている「直江兼続生誕450年 特別展・上杉家家臣団」の図録。フルカラー。今回は漢籍や藩蔵書の類は含まれていないが、家臣団の結びつきがわかる様々な古文書、資料からはいくつの示唆めいたものを得ることができた。
巻末解説「中世越後の小国氏」を執筆した矢田俊文先生からいただいた。ありがとうございました。
米沢市上杉博物館
http://www.denkoku-no-mori.yonezawa.yamagata.jp/uesugi.htm
新収 漢文と東アジア 他 ― 2010/10/22 21:35
金文京(著)『漢文と東アジア―訓読の文化圏』(岩波新書)、岩波書店、2010年8月
加地伸行(著)『漢文法基礎―本当にわかる漢文入門』(講談社学術文庫)講談社、2010年10月
吉川忠夫・船山徹(訳)『高僧伝』(4)(岩波文庫)、岩波書店、2010年9月
藤堂明保・竹田晃・影山輝國(訳注)『倭国伝』(講談社学術文庫)、講談社、2010年9月
山本忠尚(著)『高松塚・キトラ古墳の謎』吉川弘文館、2010年10月
榎本渉(著)『僧侶と海商たちの東シナ海』(講談社撰書メチエ)、講談社、2010年10月
林淳(著)『天文方と陰陽道』(日本史リブレット)、山川出版社、2006年
ここ数ヶ月に購入した新書、文庫本など。いずれもWeb上には情報がたくさんある。
上から4冊目までは訓読、翻訳の技術を学ぶ際に参考になる点が少なくない。学生に紹介したり、回読用に購入したものもある。漢文法基礎は読みやすく得るところが少なくないので漢文訓読がはじめての学生にはよさそう。少々冗長。『漢文と東アジア』は間口は狭いのに実はすごい奥行きがある店のようで、自分には得るところが多いが、学部生には少々、きつそう。
いずれの本も蘊蓄が深くて購入したはよいが、肝心な部分を吸収するには読書の時間がない。
『高僧伝』『漢文と東アジア』『倭国伝』『高松塚・キトラ古墳』に北朝関係の記事がある。
加地伸行(著)『漢文法基礎―本当にわかる漢文入門』(講談社学術文庫)講談社、2010年10月
吉川忠夫・船山徹(訳)『高僧伝』(4)(岩波文庫)、岩波書店、2010年9月
藤堂明保・竹田晃・影山輝國(訳注)『倭国伝』(講談社学術文庫)、講談社、2010年9月
山本忠尚(著)『高松塚・キトラ古墳の謎』吉川弘文館、2010年10月
榎本渉(著)『僧侶と海商たちの東シナ海』(講談社撰書メチエ)、講談社、2010年10月
林淳(著)『天文方と陰陽道』(日本史リブレット)、山川出版社、2006年
ここ数ヶ月に購入した新書、文庫本など。いずれもWeb上には情報がたくさんある。
上から4冊目までは訓読、翻訳の技術を学ぶ際に参考になる点が少なくない。学生に紹介したり、回読用に購入したものもある。漢文法基礎は読みやすく得るところが少なくないので漢文訓読がはじめての学生にはよさそう。少々冗長。『漢文と東アジア』は間口は狭いのに実はすごい奥行きがある店のようで、自分には得るところが多いが、学部生には少々、きつそう。
いずれの本も蘊蓄が深くて購入したはよいが、肝心な部分を吸収するには読書の時間がない。
『高僧伝』『漢文と東アジア』『倭国伝』『高松塚・キトラ古墳』に北朝関係の記事がある。
拝受 蝦夷地における漆器の流通と使途 ― 2010/08/04 23:02
浅倉有子、蝦夷地における漆器の流通と使途-浄法寺から平取へ、千田・矢田(編)『都市と城館の中世』、高志書院、2010年4月
浅倉有子、蝦夷地における漆器の流通と使途-椀(盃)・盃台・「台盃」-、『北海道・東北史研究』第6号、2010年年4月
浅倉有子、姥捨の月と真澄-「田毎」の景観の成立、『真澄学』第5号、2010年2月
浅倉先生からいただいた。ありがとうございました。
前二点は近世蝦夷地における漆器の流通と利用のされ方について論じている。
『真澄学』第5号
http://gs.tuad.ac.jp/tobunken/blog.php?date=2010-02-05&cID=5&keyword=&ym=
浅倉有子、蝦夷地における漆器の流通と使途-椀(盃)・盃台・「台盃」-、『北海道・東北史研究』第6号、2010年年4月
浅倉有子、姥捨の月と真澄-「田毎」の景観の成立、『真澄学』第5号、2010年2月
浅倉先生からいただいた。ありがとうございました。
前二点は近世蝦夷地における漆器の流通と利用のされ方について論じている。
『真澄学』第5号
http://gs.tuad.ac.jp/tobunken/blog.php?date=2010-02-05&cID=5&keyword=&ym=
新収 新潟史学 第63号 ― 2010/08/03 20:26
新潟史学会『新潟史学』第63号、2010年5月。
論文3点、書評・紹介3点が掲載されている。そのうち3点の題名を。
片桐昭彦「越後守護上杉家年寄の領主的展開ー越後・信濃の市川氏を中心に」
阿部哲人「上杉景勝の揚北衆掌握と直江兼続」
小宮山敏和「上越市立総合博物館編『高田藩 榊原家史料目録・研究』」
いただいた論文、購入した書籍が山積みで収拾がつかなくなりつつある。
論文3点、書評・紹介3点が掲載されている。そのうち3点の題名を。
片桐昭彦「越後守護上杉家年寄の領主的展開ー越後・信濃の市川氏を中心に」
阿部哲人「上杉景勝の揚北衆掌握と直江兼続」
小宮山敏和「上越市立総合博物館編『高田藩 榊原家史料目録・研究』」
いただいた論文、購入した書籍が山積みで収拾がつかなくなりつつある。
拝受 『紫明抄』所引『帝王略論』について ― 2010/07/12 02:45
会田大輔、『紫明抄』所引『帝王略論』について、『国語と国文学』平成二十二年三月号、2010年。
東洋史を専攻する会田さんからいただいた。ありがとうございました。
『源氏物語』の注釈書である素寂撰『紫明抄』に引用された唐代の『帝王略論』をめぐる研究。素寂がいつどこで『帝王略論』をみたのかをおっていく。そして彼との関わりが濃厚に推測できる北条氏の金沢文庫で閲覧したのだとすれば、それは1270年から1276年の間であったのではないかとする。推論を重ねてはいるが『帝王略論』や金沢文庫の研究からみてユニークな論文である。
東洋史を専攻する会田さんからいただいた。ありがとうございました。
『源氏物語』の注釈書である素寂撰『紫明抄』に引用された唐代の『帝王略論』をめぐる研究。素寂がいつどこで『帝王略論』をみたのかをおっていく。そして彼との関わりが濃厚に推測できる北条氏の金沢文庫で閲覧したのだとすれば、それは1270年から1276年の間であったのではないかとする。推論を重ねてはいるが『帝王略論』や金沢文庫の研究からみてユニークな論文である。
拝受 地震と中世の流通 ― 2010/05/18 23:17

矢田俊文(著)『地震と中世の流通』(高志書院選書6)、高志書院、2010年5月。
矢田先生からいただいた。ありがとうございました。2部構成でそれぞれが4章にわかれる。
「第I部 中世考古学と物質流通」「第II部 地震と集散地の被害」となっており、商品流通を中心に中世考古学と地震研究の成果をクロスさせるという構成を取っている。
前掲『中世の巨大地震』よりやや難易度はあがった感じだが、一般向けの内容である。
http://iwamoto.asablo.jp/blog/2009/01/07/4046288
矢田先生からいただいた。ありがとうございました。2部構成でそれぞれが4章にわかれる。
「第I部 中世考古学と物質流通」「第II部 地震と集散地の被害」となっており、商品流通を中心に中世考古学と地震研究の成果をクロスさせるという構成を取っている。
前掲『中世の巨大地震』よりやや難易度はあがった感じだが、一般向けの内容である。
http://iwamoto.asablo.jp/blog/2009/01/07/4046288
拝受 中世紀州の景観と地域社会 ― 2010/05/13 23:33

高木徳郎(著)『中世紀州の景観と地域社会』(高木徳郎発行、2010年4月)、総169頁。
学部・専攻同期の旧友で、この四月から母校の早稲田大学教育学部で教壇にあがることになった高木先生からいただいた。ありがとうございました。
和歌山での学芸員時代に執筆された解説や論文など16篇を「Ⅰ 棚田と文化的景観」「II 鞆淵と天野」「III 根来」「IV 熊野」にわけて再編集し、巻末にこれまでの業績一覧を整理されている。
すでに2008年に博論をもとに刊行した『日本中世地域環境史の研究』(校倉書房)があるので、2冊目の単著ということになる。
「地歴」出身らしく、地理学の専著が引用されているのが印象的。
学部・専攻同期の旧友で、この四月から母校の早稲田大学教育学部で教壇にあがることになった高木先生からいただいた。ありがとうございました。
和歌山での学芸員時代に執筆された解説や論文など16篇を「Ⅰ 棚田と文化的景観」「II 鞆淵と天野」「III 根来」「IV 熊野」にわけて再編集し、巻末にこれまでの業績一覧を整理されている。
すでに2008年に博論をもとに刊行した『日本中世地域環境史の研究』(校倉書房)があるので、2冊目の単著ということになる。
「地歴」出身らしく、地理学の専著が引用されているのが印象的。
拝受 図説 直江兼続 人と時代 ― 2010/04/05 22:14

阿部哲人(編)『図説 直江兼続 人と時代』、天地人博2009実行委員会・米沢上杉文化振興財団、2010年3月。
http://www.denkoku-no-mori.yonezawa.yamagata.jp/museum_shop_zurokusyosai.htm#0901
阿部さんからいただいた。ありがとうございました。こちらの事情で少々手元に届くのが遅くなり、紹介が遅れた。「天地人博2009」で企画展示された資料の内、320点を収載。フルカラーで十分すぎるほどのコンテンツである。
2007年にも図録『特別展 直江兼続』、米沢市上杉博物館(総127頁)が刊行されているが、その企画時は兼続の知名度は高いものでなく、まさかNHKドラマと重なるとは予期していなかった。某先生に「マニアックな」というお言葉をいただいた記憶がある。
しかし、その後、関連資料は幅広く集められ、研究の精度もより高いものとなった。本図録は総351頁で2倍以上の増量となっており、写真も以前より大きく見やすい。小島毅、中野等、山田邦明、八鍬友広と寄稿している先生方の顔ぶれも豪華。
http://www.denkoku-no-mori.yonezawa.yamagata.jp/museum_shop_zurokusyosai.htm#0901
阿部さんからいただいた。ありがとうございました。こちらの事情で少々手元に届くのが遅くなり、紹介が遅れた。「天地人博2009」で企画展示された資料の内、320点を収載。フルカラーで十分すぎるほどのコンテンツである。
2007年にも図録『特別展 直江兼続』、米沢市上杉博物館(総127頁)が刊行されているが、その企画時は兼続の知名度は高いものでなく、まさかNHKドラマと重なるとは予期していなかった。某先生に「マニアックな」というお言葉をいただいた記憶がある。
しかし、その後、関連資料は幅広く集められ、研究の精度もより高いものとなった。本図録は総351頁で2倍以上の増量となっており、写真も以前より大きく見やすい。小島毅、中野等、山田邦明、八鍬友広と寄稿している先生方の顔ぶれも豪華。
拝受 越後文書宝翰集 色部氏文書I ― 2010/03/17 19:38
矢田俊文・新潟県立歴史博物館(編)『越後文書宝翰集 色部氏文書 I 』、(新潟大学大域プロジェクト叢刊XV)、新潟大学「東部ユーラシア周縁世界の文化システムに関する資料学的研究」プロジェクト、2010年3月。
プロジェクト代表の関尾先生からいただいた。ありがとうございました。
越後文書宝翰集は国指定重要文化財で全体で四四巻、大きくわけて十八群あり、 本書で紹介する文書はこのうちの一群である色部氏文書の一部、第一巻から第四巻、四七点を紹介している。
フルカラーの図版編と解説編からなっている。解説は前嶋敏「「色部氏文書」と『古案記録草案』」。執筆者、編集者7名。
既刊
http://iwamoto.asablo.jp/blog/2009/03/24/4201790
プロジェクト代表の関尾先生からいただいた。ありがとうございました。
越後文書宝翰集は国指定重要文化財で全体で四四巻、大きくわけて十八群あり、 本書で紹介する文書はこのうちの一群である色部氏文書の一部、第一巻から第四巻、四七点を紹介している。
フルカラーの図版編と解説編からなっている。解説は前嶋敏「「色部氏文書」と『古案記録草案』」。執筆者、編集者7名。
既刊
http://iwamoto.asablo.jp/blog/2009/03/24/4201790
拝受 日本の村と宮座 ― 2010/03/09 18:35
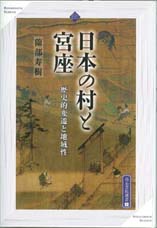
薗部寿樹(著)『日本の村と宮座』(高志書院選書5)、高志書院、2010年3月。
薗部先生からいただいた。ありがとうございました。
研究者向けの一般書(総171頁、2500円+税)。
「宮座(みやざ)」とは「神社または寺院などの場において祭祀をおこなう集団であり、祭祀のとりしきり役である頭役を宮座のメンバーが輪番につとめるという特徴」(本文より)をもっている。
本の分類や研究手法は日本史に属すが、対象の性格上、宗教社会学、民俗学的要素も感じられる。
目次はこちら
http://www.koshi-s.jp/shinkan/100303_2-shinkan.htm
また、次のような修正をいただいた(追記)。
誤 正
52頁(本文)15行目
播磨国有馬郡 → 摂津国有馬郡
92頁(本文) 15行目
南郡に二例 → 南郡に一例
139頁(引用史料)2行目 (子脱)
若王子大明神 → 若王大明神
139頁(引用史料)6行目
栩原祭り → 大宮栩原祭り
139頁(本文)9行目
五十間四方(約九九メートル) →五十間四方(約九一メートル)
141頁(引用史料)2~3行目
小房・弐ヶ村 → 小房弐ヶ村
141頁(本文)9行目
小房・弐ヶ → 小房弐ヶ村
なお、以前にリンクのような関係論文をいただいている。
http://iwamoto.asablo.jp/blog/2009/06/11/
勤務先でも刊行ラッシュがはじまりつつあるが、もう少しためておこう。
薗部先生からいただいた。ありがとうございました。
研究者向けの一般書(総171頁、2500円+税)。
「宮座(みやざ)」とは「神社または寺院などの場において祭祀をおこなう集団であり、祭祀のとりしきり役である頭役を宮座のメンバーが輪番につとめるという特徴」(本文より)をもっている。
本の分類や研究手法は日本史に属すが、対象の性格上、宗教社会学、民俗学的要素も感じられる。
目次はこちら
http://www.koshi-s.jp/shinkan/100303_2-shinkan.htm
また、次のような修正をいただいた(追記)。
誤 正
52頁(本文)15行目
播磨国有馬郡 → 摂津国有馬郡
92頁(本文) 15行目
南郡に二例 → 南郡に一例
139頁(引用史料)2行目 (子脱)
若王子大明神 → 若王大明神
139頁(引用史料)6行目
栩原祭り → 大宮栩原祭り
139頁(本文)9行目
五十間四方(約九九メートル) →五十間四方(約九一メートル)
141頁(引用史料)2~3行目
小房・弐ヶ村 → 小房弐ヶ村
141頁(本文)9行目
小房・弐ヶ → 小房弐ヶ村
なお、以前にリンクのような関係論文をいただいている。
http://iwamoto.asablo.jp/blog/2009/06/11/
勤務先でも刊行ラッシュがはじまりつつあるが、もう少しためておこう。