Web版 吐魯番出土文物研究情報集録 1988-1996 ― 2012/01/13 03:10
ここ数年で
荒川正晴(著)『ユーラシアの交通・交易と唐帝国』、名古屋大学出版会、2010年12月。 http://iwamoto.asablo.jp/blog/2010/12/20/
關尾史郎(著)『もうひとつの敦煌―鎮墓瓶と画像磚の世界』(新大人文叢書7)、高志書院、2011年3月。 http://iwamoto.asablo.jp/blog/2011/04/25/
といった成果が公刊されており、いずれにも『吐魯番出土文物研究情報集録』が引用されているか、その成果が基礎とされている部分が見受けられる。ただ紙媒体の『吐魯番出土文物研究情報集録』の入手はたいへん困難である。
2003年の前後数年、「新潟大学・人文・敦煌プロジェクト」サイトにて公開していたのだが、サーバの老朽化によりサイト自体が消滅、このたび別の検索エンジンをつかい、下記アドレスに復活させた。全文PDFで読むことができるほか記事作者名や記事題名で検索可能である。若干斜めにスキャンされているところもあるが、読めるということでご容赦願いたい。
吐魯番出土文物研究情報集録(No.1-108号、1988-1996)
http://www.human.niigata-u.ac.jp/~ssekio/turfan/
このブログは一ヶ月ぶりの更新となってしまった。いただいたものもあるし購入して山積みになったものもあるわけだが…。
(追記)
集録について。
・別冊(1~50号総目次) のリンクが適切ではありません。別冊Ⅱ(1~100号総目次)を参照してください
荒川正晴(著)『ユーラシアの交通・交易と唐帝国』、名古屋大学出版会、2010年12月。 http://iwamoto.asablo.jp/blog/2010/12/20/
關尾史郎(著)『もうひとつの敦煌―鎮墓瓶と画像磚の世界』(新大人文叢書7)、高志書院、2011年3月。 http://iwamoto.asablo.jp/blog/2011/04/25/
といった成果が公刊されており、いずれにも『吐魯番出土文物研究情報集録』が引用されているか、その成果が基礎とされている部分が見受けられる。ただ紙媒体の『吐魯番出土文物研究情報集録』の入手はたいへん困難である。
2003年の前後数年、「新潟大学・人文・敦煌プロジェクト」サイトにて公開していたのだが、サーバの老朽化によりサイト自体が消滅、このたび別の検索エンジンをつかい、下記アドレスに復活させた。全文PDFで読むことができるほか記事作者名や記事題名で検索可能である。若干斜めにスキャンされているところもあるが、読めるということでご容赦願いたい。
吐魯番出土文物研究情報集録(No.1-108号、1988-1996)
http://www.human.niigata-u.ac.jp/~ssekio/turfan/
このブログは一ヶ月ぶりの更新となってしまった。いただいたものもあるし購入して山積みになったものもあるわけだが…。
(追記)
集録について。
・別冊(1~50号総目次) のリンクが適切ではありません。別冊Ⅱ(1~100号総目次)を参照してください
拝受 敦煌出土のウイグル語暦占文書・西魏北魏の二四軍と府兵制 ― 2011/10/27 02:17
松井太、敦煌出土のウイグル語暦占文書、『人文社會論叢』(弘前大学)第26号、2011年8月。
平田陽一郎、西魏北魏の二四軍と府兵制 、『東洋史研究』第70巻2号、2011年9月。
松井先生と平田先生から抜き刷りをいただいた。ありがとうございました。
ともに大変おもしろい論文で紹介済み。
http://iwamoto.asablo.jp/blog/2011/09/20/6108494
http://iwamoto.asablo.jp/blog/2011/10/14/6157023
これは何か、これは本当か、素朴な疑問や興味をもつことがある。そしてそれがなぜかわかったとき、ものすごく驚いたりうれしかったりするわけだが、そういう知的快感を得られる技術や技法があるならば、それはそれだけでこの世に存在する価値があるといえるだろう。そしてそれを他人に伝えるにはその考え方の過程を披露する以外の方法はない。
平田陽一郎、西魏北魏の二四軍と府兵制 、『東洋史研究』第70巻2号、2011年9月。
松井先生と平田先生から抜き刷りをいただいた。ありがとうございました。
ともに大変おもしろい論文で紹介済み。
http://iwamoto.asablo.jp/blog/2011/09/20/6108494
http://iwamoto.asablo.jp/blog/2011/10/14/6157023
これは何か、これは本当か、素朴な疑問や興味をもつことがある。そしてそれがなぜかわかったとき、ものすごく驚いたりうれしかったりするわけだが、そういう知的快感を得られる技術や技法があるならば、それはそれだけでこの世に存在する価値があるといえるだろう。そしてそれを他人に伝えるにはその考え方の過程を披露する以外の方法はない。
新収 東洋史研究 第70巻2号 ― 2011/10/14 23:09
『東洋史研究』第70巻2号、2011年9月。
川本芳昭、北魏内朝再論-比較史の観点から見た
平田陽一郎、西魏北魏の二四軍と府兵制
実に興味深い2本。ただともにわかりやすいかというとそうではない。それでとりあえずざっとよんでみて、あとで読み返すことにしようと思う。誤読していたとしてもこの程度の紹介文としては許していただけるであろうと思いつつ。以下はそのためのメモ。
前者。北魏の部族解散や内朝の問題について研究史をリードしてきた筆者が近年の「胡漢対立」を相対化しがちな研究動向を批判しつつ、「北魏前期国家と北魏国家とを断絶してとらえることなく、北アジア、東アジア史全体の中で」位置づける方法をあらためて模索したもの。なお前提として北魏前半期を北方的体制、後半期を胡漢融合の度合いの強い中国的中原王朝ととらえている。
論者がとくに注目しているのは北魏特有の制度である「ケシク的な」内朝制度であり、それが東アジアの諸国家や中国歴代王朝と比較してどのような性格をもつといえるか、倭国と北魏、漢の中朝と北魏の内朝という比較によって、その性格を述べている。
後者。その時代の史料にはでてこない語彙であるにもかかわらず西魏北周の基盤となる軍事制度とされてきた「府兵制」の虚構性(府兵制はなかった)を明確に指摘。葬りさったうえで、当該時代の軍事制度はどのようなものであったのかを論じる。
かわりに実態として見えてくる二四軍制は漢人主体でなく、非漢族集団をとりこんでそれを基本単位に成り立ったものであることを史料をあげて述べ、北魏ー西魏・北周の軍事機構の求心的運用が北魏の内官の系譜上にある役職「親信」「庫真」(都督)によって可能となっていたことを指摘、二四軍制とは鮮卑的軍制の上になりたっていたものと論じる。
またこれまで「府兵制」の兵士の徴発方式の変化(兵民一致⇄兵民分離)を示す史料と理解されてきた隋「開皇十年詔」について、平陳後、流寓の兵戸を関中周辺に帰農させ、一般編戸並みとする「復員令」と解釈し、従来の見方を否定する(!)。
そのうえで北魏の「部族解散」の史料をあげ、それもまた鮮卑的「復員令」(各部族を戦闘状態から平時にもどす)であり、国を挙げた戦争後においては北魏以前からみられるものであることを先行研究をふまえて述べる。
つまり、北魏ー隋の軍事制度(前秦あたりを淵源とする)がほとんど同一の構造をなしていることを論証しようとしたことになる。
後者には川本先生の旧論を前提に論じられている部分もあるが、基本的に両論の北朝観は相容れないといってよい。これを後の研究者がどう読むか、実に興味深い1冊となっている。
川本芳昭、北魏内朝再論-比較史の観点から見た
平田陽一郎、西魏北魏の二四軍と府兵制
実に興味深い2本。ただともにわかりやすいかというとそうではない。それでとりあえずざっとよんでみて、あとで読み返すことにしようと思う。誤読していたとしてもこの程度の紹介文としては許していただけるであろうと思いつつ。以下はそのためのメモ。
前者。北魏の部族解散や内朝の問題について研究史をリードしてきた筆者が近年の「胡漢対立」を相対化しがちな研究動向を批判しつつ、「北魏前期国家と北魏国家とを断絶してとらえることなく、北アジア、東アジア史全体の中で」位置づける方法をあらためて模索したもの。なお前提として北魏前半期を北方的体制、後半期を胡漢融合の度合いの強い中国的中原王朝ととらえている。
論者がとくに注目しているのは北魏特有の制度である「ケシク的な」内朝制度であり、それが東アジアの諸国家や中国歴代王朝と比較してどのような性格をもつといえるか、倭国と北魏、漢の中朝と北魏の内朝という比較によって、その性格を述べている。
後者。その時代の史料にはでてこない語彙であるにもかかわらず西魏北周の基盤となる軍事制度とされてきた「府兵制」の虚構性(府兵制はなかった)を明確に指摘。葬りさったうえで、当該時代の軍事制度はどのようなものであったのかを論じる。
かわりに実態として見えてくる二四軍制は漢人主体でなく、非漢族集団をとりこんでそれを基本単位に成り立ったものであることを史料をあげて述べ、北魏ー西魏・北周の軍事機構の求心的運用が北魏の内官の系譜上にある役職「親信」「庫真」(都督)によって可能となっていたことを指摘、二四軍制とは鮮卑的軍制の上になりたっていたものと論じる。
またこれまで「府兵制」の兵士の徴発方式の変化(兵民一致⇄兵民分離)を示す史料と理解されてきた隋「開皇十年詔」について、平陳後、流寓の兵戸を関中周辺に帰農させ、一般編戸並みとする「復員令」と解釈し、従来の見方を否定する(!)。
そのうえで北魏の「部族解散」の史料をあげ、それもまた鮮卑的「復員令」(各部族を戦闘状態から平時にもどす)であり、国を挙げた戦争後においては北魏以前からみられるものであることを先行研究をふまえて述べる。
つまり、北魏ー隋の軍事制度(前秦あたりを淵源とする)がほとんど同一の構造をなしていることを論証しようとしたことになる。
後者には川本先生の旧論を前提に論じられている部分もあるが、基本的に両論の北朝観は相容れないといってよい。これを後の研究者がどう読むか、実に興味深い1冊となっている。
拝受 出土刻字資料研究における新しい可能性に向けて ― 2011/10/05 00:55
室山留美子、出土刻字資料研究における新しい可能性に向けて-北魏墓誌を中心に、『中国史学』第20巻、2010年10月。
室山さんからいただいた。ありがとうございました。
ここ数十年間において多数の墓誌が発見され史資料が増大しているが、同時に偽刻も増えている。その真贋をみきわめ、確かな史料として扱う方法論または資料論の確立を意識した内容。墓誌の作成時期とその特徴に政治史的背景が一定の相関性をもつことを指摘する。
室山さんからいただいた。ありがとうございました。
ここ数十年間において多数の墓誌が発見され史資料が増大しているが、同時に偽刻も増えている。その真贋をみきわめ、確かな史料として扱う方法論または資料論の確立を意識した内容。墓誌の作成時期とその特徴に政治史的背景が一定の相関性をもつことを指摘する。
拝受 北魏墓誌中の銘辞 ― 2011/09/30 19:17
窪添慶文、北魏墓誌中の銘辞、『立正大学文学部論叢』第133号、2011年3月。
窪添先生からいただいた。ありがとうございました。
墓主の事蹟を示した誌文の最後に付される見落とされがちな銘辞の内容や表現の分析から、北魏期におけるその定型化の過程をおったもの。西晋、南朝墓誌の分析を通して、それが北魏墓誌の定型化に影響していたことを説く。
窪添先生からいただいた。ありがとうございました。
墓主の事蹟を示した誌文の最後に付される見落とされがちな銘辞の内容や表現の分析から、北魏期におけるその定型化の過程をおったもの。西晋、南朝墓誌の分析を通して、それが北魏墓誌の定型化に影響していたことを説く。
拝受 中国南北朝隋唐期をめぐる仏教社会史研究の地平 ― 2011/09/16 20:58
氣賀澤保規、中国南北朝隋唐期をめぐる仏教社会史研究の地平、『佛教史学研究』第53巻第1号、2010年11月。
氣賀澤先生からいただいた。ありがとうございました。
学会の基調報告の講演録。中国南北朝隋唐期の仏教史のこれまでの動向と今後の研究への提言、期待などが述べられている。宗派仏教をこえた「時代の中で仏教を捉える」研究への展開の期待や、京大人文研が培ってきた共同研究の土台への羨望なども記されている。
ただ最後の点は、関東圏では同じ機関が主導的に、かつ定期的に世代交代をしながら場を提供してきたのでなく、特定のある先生のもとに集まるという形が多いため、機関としては語りにくいわけだが、同様に開かれた共同研究や史料講読会はあったし、今もある(関西の他大にも同様に開かれた場がある)と思うのだが。
氣賀澤先生からいただいた。ありがとうございました。
学会の基調報告の講演録。中国南北朝隋唐期の仏教史のこれまでの動向と今後の研究への提言、期待などが述べられている。宗派仏教をこえた「時代の中で仏教を捉える」研究への展開の期待や、京大人文研が培ってきた共同研究の土台への羨望なども記されている。
ただ最後の点は、関東圏では同じ機関が主導的に、かつ定期的に世代交代をしながら場を提供してきたのでなく、特定のある先生のもとに集まるという形が多いため、機関としては語りにくいわけだが、同様に開かれた共同研究や史料講読会はあったし、今もある(関西の他大にも同様に開かれた場がある)と思うのだが。
拝受 水経注疏訳注 ― 2011/08/18 19:15
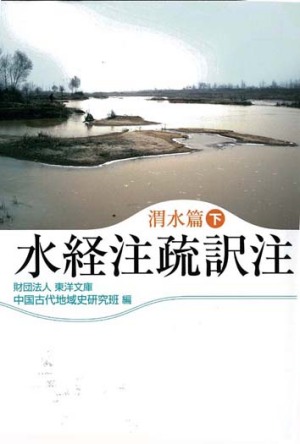
財団法人東洋文庫中国古代地域史研究班(編)『水経注疏訳注・渭水篇(下) 』(東洋文庫論叢74)東洋文庫、2011年3月。
研究班からいただいた。ありがとうございました。研究班の講読会による成果である水経注疏の現代語訳を中心に、解説、テキストの影印、地図などが含まれる。
解説・論考部分は以下のとおり。
窪添慶文、魏晋南北朝時期の長安
池田雄一、『水経注疏』関係檔案と同書稿本
池田雄一・多田狷介・石黒ひさ子・山元貴尚、傅斯年図書館所蔵『水経注疏』関係の檔案
太田幸男、陳橋駅先生との会見記
多田狷介、西安考古訪問記
渭水篇(上)
http://iwamoto.asablo.jp/blog/2008/05/23/3538371
以下個人的雑記
昨年まではCO2削減、今年は節電など様々な理由が付いて、ここ数年、決まった期間に全教職員半ば強制的に休暇を取ることになっている。ただその施策には単に右向け右的な雰囲気を感じないでもないがやむを得ない。その間、きわめて短期間ではあったが帰省した。盆や法事を意識しなくてはならない身になったこともある。
しばらく空調をつかわなかったためか、ろくに運動もせず歳ばかりとったせいか、新幹線のきつい空調や太平洋側の気候の落差には適応できなかったようで、ひどいめまいとともに体調を崩す。ついでに以前デスクトップを廃しメインマシンにしたノートがブルースクリーン頻発。なんとか窮地は脱したがOSが起動せず。MBRの破損かと思い、bootrec等のコマンドをつかったが起動せず。Windowsはいつも安全な機械なんてないことを勉強させてくれる。おかげでバックアップと代替準備は完璧。ただ使いやすい環境の再構築には時間がかかる。パフォーマンスが落ちたのは否めない。
暑さと不安定な体調、そして焦燥感にさいなまれる。
研究班からいただいた。ありがとうございました。研究班の講読会による成果である水経注疏の現代語訳を中心に、解説、テキストの影印、地図などが含まれる。
解説・論考部分は以下のとおり。
窪添慶文、魏晋南北朝時期の長安
池田雄一、『水経注疏』関係檔案と同書稿本
池田雄一・多田狷介・石黒ひさ子・山元貴尚、傅斯年図書館所蔵『水経注疏』関係の檔案
太田幸男、陳橋駅先生との会見記
多田狷介、西安考古訪問記
渭水篇(上)
http://iwamoto.asablo.jp/blog/2008/05/23/3538371
以下個人的雑記
昨年まではCO2削減、今年は節電など様々な理由が付いて、ここ数年、決まった期間に全教職員半ば強制的に休暇を取ることになっている。ただその施策には単に右向け右的な雰囲気を感じないでもないがやむを得ない。その間、きわめて短期間ではあったが帰省した。盆や法事を意識しなくてはならない身になったこともある。
しばらく空調をつかわなかったためか、ろくに運動もせず歳ばかりとったせいか、新幹線のきつい空調や太平洋側の気候の落差には適応できなかったようで、ひどいめまいとともに体調を崩す。ついでに以前デスクトップを廃しメインマシンにしたノートがブルースクリーン頻発。なんとか窮地は脱したがOSが起動せず。MBRの破損かと思い、bootrec等のコマンドをつかったが起動せず。Windowsはいつも安全な機械なんてないことを勉強させてくれる。おかげでバックアップと代替準備は完璧。ただ使いやすい環境の再構築には時間がかかる。パフォーマンスが落ちたのは否めない。
暑さと不安定な体調、そして焦燥感にさいなまれる。
新収 東方学 第122輯 ― 2011/08/08 19:19
『東方学』第122輯、2011年7月
戸川貴行、東晋南朝における伝統の創造について―楽曲編成を中心としてみた
渡辺信一郎氏によって掘り下げられてきたテーマである国家儀礼に不可欠な雅楽がもつ政治的イデオロギーに注目、とくに劉宋孝武帝にいたるまでの整備状況を分析したもの。またそこに付加されていった北朝期における『周礼』的要素を意識しつつ、南朝の「伝統」が南北朝隋唐政権の帝国理念の形成に与えた影響を視野に入れて論が展開される。
南北朝隋唐論であり、中華的世界観の分析のひとつにもなっている。
『新修本草』序例もこうした中華的世界観で書かれているわけで、個々の語彙の歴史をしるうえで勉強になる箇所もあった。
まったく雑感ではあるが、様々な言語でまた様々な形での「史料」が増大しつつある昨今、王朝の世界観の発展やその変化によって中国史を語ることの現代的意義、またそれを「中国」に住んでいない日本の研究者が語る意義は、熟考する必要があると思っている。史書から取り出された世界観は権力の本質を分析する一視点として有効である。
ではそこからみいだされるものが「歴史」なのか。もっと多彩な視点からその時代を描けるのではないか。その視点のおきかたを自分で考えてみることが目下の関心である。
戸川貴行、東晋南朝における伝統の創造について―楽曲編成を中心としてみた
渡辺信一郎氏によって掘り下げられてきたテーマである国家儀礼に不可欠な雅楽がもつ政治的イデオロギーに注目、とくに劉宋孝武帝にいたるまでの整備状況を分析したもの。またそこに付加されていった北朝期における『周礼』的要素を意識しつつ、南朝の「伝統」が南北朝隋唐政権の帝国理念の形成に与えた影響を視野に入れて論が展開される。
南北朝隋唐論であり、中華的世界観の分析のひとつにもなっている。
『新修本草』序例もこうした中華的世界観で書かれているわけで、個々の語彙の歴史をしるうえで勉強になる箇所もあった。
まったく雑感ではあるが、様々な言語でまた様々な形での「史料」が増大しつつある昨今、王朝の世界観の発展やその変化によって中国史を語ることの現代的意義、またそれを「中国」に住んでいない日本の研究者が語る意義は、熟考する必要があると思っている。史書から取り出された世界観は権力の本質を分析する一視点として有効である。
ではそこからみいだされるものが「歴史」なのか。もっと多彩な視点からその時代を描けるのではないか。その視点のおきかたを自分で考えてみることが目下の関心である。
新収 魏晋南北朝唐宋考古文稿輯叢 ほか ― 2011/08/01 18:34
宿白(著)『魏晋南北朝唐宋考古文稿輯叢』、文物出版社、2011年1月。
許逸民(校箋)『金楼子校箋』、中華書局、2011年1月。
前者は宿白氏がこれまで『文物』などに掲載してきた魏晋南北朝唐宋考古に関する論文を集めて整理したもの。古い記事でも自分にとっては北朝考古系でとくに興味深い記事が多い。金楼子は南朝梁の蕭繹の著作。南北朝史の研究者にはよく知られた本だと思っていたが、基本的に永楽大典にあつめられたものが今に伝わるもので、CiNiiiで検索するとこの書名を題名につけているのは日本語の論文では5点のみ。点校本がでるのははじめてだということで購入。典籍関係で興味深い記事がある記憶だったが、どちらかというと晋南朝の故事、志怪の記事が主体。また家訓的要素ももつとの先行研究の分析があるとおり。点校本がでたことでさらに今後頻用される気がする。
許逸民(校箋)『金楼子校箋』、中華書局、2011年1月。
前者は宿白氏がこれまで『文物』などに掲載してきた魏晋南北朝唐宋考古に関する論文を集めて整理したもの。古い記事でも自分にとっては北朝考古系でとくに興味深い記事が多い。金楼子は南朝梁の蕭繹の著作。南北朝史の研究者にはよく知られた本だと思っていたが、基本的に永楽大典にあつめられたものが今に伝わるもので、CiNiiiで検索するとこの書名を題名につけているのは日本語の論文では5点のみ。点校本がでるのははじめてだということで購入。典籍関係で興味深い記事がある記憶だったが、どちらかというと晋南朝の故事、志怪の記事が主体。また家訓的要素ももつとの先行研究の分析があるとおり。点校本がでたことでさらに今後頻用される気がする。
拝受 新出北朝隋代墓誌所在総合目録(2006-2010年) ほか ― 2011/07/26 17:30
梶山智史、新出北朝隋代墓誌所在総合目録(2006-2010年)、『東アジア石刻研究』第3号、2011年3月
梶山智史、(書評)高橋継男編『中国石刻関係図書目録(1949-2007)』、『唐代史研究』第13号、2010年8月
張金龍(著)梶山智史(訳)、北魏の狩猟図とその淵源、『明大アジア史論集』第14号、2010年3月。
梶山さんからいただいた。ありがとうございました。
新出北朝隋代墓誌所在総合目録は氣賀澤(編)『唐代墓誌・・』の姉妹編にあたり、本誌第1号に掲載された目録の続編。356方の情報を載せる。
この目録を見ただけでもわかるが、歴代の金石録に載っている以外、ここ20年ほどに発見された墓誌に限っても相当な数で、特に近年その増加は著しい。
正史に名が見えるものの立伝されていない重要人物や、史書に記載のない墓主名に絞った場合でも、各王朝いずれでも、外伝2,3冊分をこえる字数の史料が増えているといってよい。唐代にいたっては閲覧しきれないほどの量である。なお、北朝の墓誌資料には当然、南朝諸政権(特に梁陳)との関係を考えるさいに有効な記事がままみられるし、唐代墓誌にも南北朝期を考える手がかりがみられる。
張金龍論文は大同、固原、ホリンゴル、盛楽などから発見された壁画、棺板画に描かれた北魏期の狩猟図について論じたもの。ササン朝ペルシアの狩猟図の影響より、漢の画像石や魏晋の壁画墓とのつながりが強いものとみる。
梶山智史、(書評)高橋継男編『中国石刻関係図書目録(1949-2007)』、『唐代史研究』第13号、2010年8月
張金龍(著)梶山智史(訳)、北魏の狩猟図とその淵源、『明大アジア史論集』第14号、2010年3月。
梶山さんからいただいた。ありがとうございました。
新出北朝隋代墓誌所在総合目録は氣賀澤(編)『唐代墓誌・・』の姉妹編にあたり、本誌第1号に掲載された目録の続編。356方の情報を載せる。
この目録を見ただけでもわかるが、歴代の金石録に載っている以外、ここ20年ほどに発見された墓誌に限っても相当な数で、特に近年その増加は著しい。
正史に名が見えるものの立伝されていない重要人物や、史書に記載のない墓主名に絞った場合でも、各王朝いずれでも、外伝2,3冊分をこえる字数の史料が増えているといってよい。唐代にいたっては閲覧しきれないほどの量である。なお、北朝の墓誌資料には当然、南朝諸政権(特に梁陳)との関係を考えるさいに有効な記事がままみられるし、唐代墓誌にも南北朝期を考える手がかりがみられる。
張金龍論文は大同、固原、ホリンゴル、盛楽などから発見された壁画、棺板画に描かれた北魏期の狩猟図について論じたもの。ササン朝ペルシアの狩猟図の影響より、漢の画像石や魏晋の壁画墓とのつながりが強いものとみる。