拝受 出土刻字資料研究における新しい可能性に向けて ― 2011/10/05 00:55
室山留美子、出土刻字資料研究における新しい可能性に向けて-北魏墓誌を中心に、『中国史学』第20巻、2010年10月。
室山さんからいただいた。ありがとうございました。
ここ数十年間において多数の墓誌が発見され史資料が増大しているが、同時に偽刻も増えている。その真贋をみきわめ、確かな史料として扱う方法論または資料論の確立を意識した内容。墓誌の作成時期とその特徴に政治史的背景が一定の相関性をもつことを指摘する。
室山さんからいただいた。ありがとうございました。
ここ数十年間において多数の墓誌が発見され史資料が増大しているが、同時に偽刻も増えている。その真贋をみきわめ、確かな史料として扱う方法論または資料論の確立を意識した内容。墓誌の作成時期とその特徴に政治史的背景が一定の相関性をもつことを指摘する。
新収 東洋史研究 第70巻2号 ― 2011/10/14 23:09
『東洋史研究』第70巻2号、2011年9月。
川本芳昭、北魏内朝再論-比較史の観点から見た
平田陽一郎、西魏北魏の二四軍と府兵制
実に興味深い2本。ただともにわかりやすいかというとそうではない。それでとりあえずざっとよんでみて、あとで読み返すことにしようと思う。誤読していたとしてもこの程度の紹介文としては許していただけるであろうと思いつつ。以下はそのためのメモ。
前者。北魏の部族解散や内朝の問題について研究史をリードしてきた筆者が近年の「胡漢対立」を相対化しがちな研究動向を批判しつつ、「北魏前期国家と北魏国家とを断絶してとらえることなく、北アジア、東アジア史全体の中で」位置づける方法をあらためて模索したもの。なお前提として北魏前半期を北方的体制、後半期を胡漢融合の度合いの強い中国的中原王朝ととらえている。
論者がとくに注目しているのは北魏特有の制度である「ケシク的な」内朝制度であり、それが東アジアの諸国家や中国歴代王朝と比較してどのような性格をもつといえるか、倭国と北魏、漢の中朝と北魏の内朝という比較によって、その性格を述べている。
後者。その時代の史料にはでてこない語彙であるにもかかわらず西魏北周の基盤となる軍事制度とされてきた「府兵制」の虚構性(府兵制はなかった)を明確に指摘。葬りさったうえで、当該時代の軍事制度はどのようなものであったのかを論じる。
かわりに実態として見えてくる二四軍制は漢人主体でなく、非漢族集団をとりこんでそれを基本単位に成り立ったものであることを史料をあげて述べ、北魏ー西魏・北周の軍事機構の求心的運用が北魏の内官の系譜上にある役職「親信」「庫真」(都督)によって可能となっていたことを指摘、二四軍制とは鮮卑的軍制の上になりたっていたものと論じる。
またこれまで「府兵制」の兵士の徴発方式の変化(兵民一致⇄兵民分離)を示す史料と理解されてきた隋「開皇十年詔」について、平陳後、流寓の兵戸を関中周辺に帰農させ、一般編戸並みとする「復員令」と解釈し、従来の見方を否定する(!)。
そのうえで北魏の「部族解散」の史料をあげ、それもまた鮮卑的「復員令」(各部族を戦闘状態から平時にもどす)であり、国を挙げた戦争後においては北魏以前からみられるものであることを先行研究をふまえて述べる。
つまり、北魏ー隋の軍事制度(前秦あたりを淵源とする)がほとんど同一の構造をなしていることを論証しようとしたことになる。
後者には川本先生の旧論を前提に論じられている部分もあるが、基本的に両論の北朝観は相容れないといってよい。これを後の研究者がどう読むか、実に興味深い1冊となっている。
川本芳昭、北魏内朝再論-比較史の観点から見た
平田陽一郎、西魏北魏の二四軍と府兵制
実に興味深い2本。ただともにわかりやすいかというとそうではない。それでとりあえずざっとよんでみて、あとで読み返すことにしようと思う。誤読していたとしてもこの程度の紹介文としては許していただけるであろうと思いつつ。以下はそのためのメモ。
前者。北魏の部族解散や内朝の問題について研究史をリードしてきた筆者が近年の「胡漢対立」を相対化しがちな研究動向を批判しつつ、「北魏前期国家と北魏国家とを断絶してとらえることなく、北アジア、東アジア史全体の中で」位置づける方法をあらためて模索したもの。なお前提として北魏前半期を北方的体制、後半期を胡漢融合の度合いの強い中国的中原王朝ととらえている。
論者がとくに注目しているのは北魏特有の制度である「ケシク的な」内朝制度であり、それが東アジアの諸国家や中国歴代王朝と比較してどのような性格をもつといえるか、倭国と北魏、漢の中朝と北魏の内朝という比較によって、その性格を述べている。
後者。その時代の史料にはでてこない語彙であるにもかかわらず西魏北周の基盤となる軍事制度とされてきた「府兵制」の虚構性(府兵制はなかった)を明確に指摘。葬りさったうえで、当該時代の軍事制度はどのようなものであったのかを論じる。
かわりに実態として見えてくる二四軍制は漢人主体でなく、非漢族集団をとりこんでそれを基本単位に成り立ったものであることを史料をあげて述べ、北魏ー西魏・北周の軍事機構の求心的運用が北魏の内官の系譜上にある役職「親信」「庫真」(都督)によって可能となっていたことを指摘、二四軍制とは鮮卑的軍制の上になりたっていたものと論じる。
またこれまで「府兵制」の兵士の徴発方式の変化(兵民一致⇄兵民分離)を示す史料と理解されてきた隋「開皇十年詔」について、平陳後、流寓の兵戸を関中周辺に帰農させ、一般編戸並みとする「復員令」と解釈し、従来の見方を否定する(!)。
そのうえで北魏の「部族解散」の史料をあげ、それもまた鮮卑的「復員令」(各部族を戦闘状態から平時にもどす)であり、国を挙げた戦争後においては北魏以前からみられるものであることを先行研究をふまえて述べる。
つまり、北魏ー隋の軍事制度(前秦あたりを淵源とする)がほとんど同一の構造をなしていることを論証しようとしたことになる。
後者には川本先生の旧論を前提に論じられている部分もあるが、基本的に両論の北朝観は相容れないといってよい。これを後の研究者がどう読むか、実に興味深い1冊となっている。
拝受 大谷光瑞と国際政治社会-チベット・探検隊・辛亥革命 ― 2011/10/24 21:09
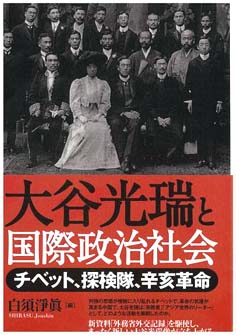
白須淨眞(編)『大谷光瑞と国際政治社会-チベット・探検隊・辛亥革命』勉誠出版、2011年10月。
柴田幹夫「辛亥革命と大谷光瑞」(上記『大谷光瑞と国際政治社会-チベット・探検隊・辛亥革命』所収)。
執筆者のお一人の柴田幹夫先生から抜き刷りとともにいただいた。ありがとうございました。執筆者は以下のとおり。
金子民雄、白須淨眞、ブリッジ・タンカ、奥山直司、高本康子、柴田幹夫、加藤斗規
今年は辛亥革命100年であるという意味でタイムリーである。帯には「新資料「外務省外交記録」を駆使し、まったく新しい大谷光瑞像が立ち上がる」とある。また大谷光瑞と取り巻く人々の活動を見ていくとチベット問題を避けて通れないことが注目されているようである。(これから読みます)
目次や詳しい紹介はこちら(勉誠出版)。
http://bensei.jp/index.php?main_page=product_book_info&products_id=100043
また、昨年にも柴田幹夫(編)『大谷光瑞とアジア』なる本が刊行されている。 http://iwamoto.asablo.jp/blog/2010/08/10/5278477
さてここ数日、締め切りつきの書類、原稿におわれていてブログを書く暇もなかった。(すいません。某所で、「できれば」10月中にと依頼された原稿はできてません。)ただこんな中でも抜き刷りをいただいたり、書籍を(大量に)購入しているのでおって書き込んでいくことにしたい。
柴田幹夫「辛亥革命と大谷光瑞」(上記『大谷光瑞と国際政治社会-チベット・探検隊・辛亥革命』所収)。
執筆者のお一人の柴田幹夫先生から抜き刷りとともにいただいた。ありがとうございました。執筆者は以下のとおり。
金子民雄、白須淨眞、ブリッジ・タンカ、奥山直司、高本康子、柴田幹夫、加藤斗規
今年は辛亥革命100年であるという意味でタイムリーである。帯には「新資料「外務省外交記録」を駆使し、まったく新しい大谷光瑞像が立ち上がる」とある。また大谷光瑞と取り巻く人々の活動を見ていくとチベット問題を避けて通れないことが注目されているようである。(これから読みます)
目次や詳しい紹介はこちら(勉誠出版)。
http://bensei.jp/index.php?main_page=product_book_info&products_id=100043
また、昨年にも柴田幹夫(編)『大谷光瑞とアジア』なる本が刊行されている。 http://iwamoto.asablo.jp/blog/2010/08/10/5278477
さてここ数日、締め切りつきの書類、原稿におわれていてブログを書く暇もなかった。(すいません。某所で、「できれば」10月中にと依頼された原稿はできてません。)ただこんな中でも抜き刷りをいただいたり、書籍を(大量に)購入しているのでおって書き込んでいくことにしたい。
「日本」国号に関する報道、記事 ― 2011/10/25 03:26
「日本」呼称、最古の例か 678年の墓誌?中国で発見(asahi.com)
気賀沢保規先生のコメントがついている。
http://www.asahi.com/culture/update/1022/TKY201110220586.html
以下のサイトのコメントが大変、参考になる。
天武天皇7年(678)には既に用いられていた「日本」国号: 王連龍「百済人《禰軍墓誌》考論」(石井公成先生の「聖徳太子研究の最前線」blog)
http://blog.goo.ne.jp/kosei-gooblog/e/83d4a0170e3ffd13634b4f6dcd46bd95
気賀沢保規先生のコメントがついている。
http://www.asahi.com/culture/update/1022/TKY201110220586.html
以下のサイトのコメントが大変、参考になる。
天武天皇7年(678)には既に用いられていた「日本」国号: 王連龍「百済人《禰軍墓誌》考論」(石井公成先生の「聖徳太子研究の最前線」blog)
http://blog.goo.ne.jp/kosei-gooblog/e/83d4a0170e3ffd13634b4f6dcd46bd95
大学院、来年度から修士論文不要に 試験などで審査 ― 2011/10/27 00:22
大学院、来年度から修士論文不要に 試験などで審査
http://www.nikkei.com/news/headline/article/g=96958A9C93819695E0E4E2E6EB8DE0E4E3E2E0E2E3E39180EAE2E2E2
「広い視野と能力を持った人材を育てるのが狙い。従来の修士課程は論文作成のため早い段階から特定の研究室に所属して研究テーマを絞ることが多く、博士課程を終えても産業界から「専門分野には詳しいが応用が利かず、使いにくい」と評価されてきた。」(日本経済新聞 2011/10/26)
「広い視野と能力」はペーパー試験と面接で評価できるという理解らしい。海外の大学院などに「部分的」にならった制度なのかもしれないが、形だけの試験のようなものになってしまう可能性もあろう。そもそもその新制度を運用するのはそれまで別の方法を主導してきた教員なのだから。
一方、論文作成指導の過程でしか養えないような個人的探求心や分析力、叙述力といった能力もあるはずだが、それを身につけたものがかりに「専門分野には詳しいが応用が利かず、使いにくい」人材となってしまうのだとして、その原因はやはり修士論文という審査方法にあるといえるのだろうか。論文を指導する側に問題があったり、受け皿となる産業界にこそそうした能力を引き出す応用力を補填する必要はないのだろうか。
この提案(方針)は 「博士号取得を目指す大学院生が主な対象」だそうだが、博士論文までを免除する気はないようである。それなのに 「博士号取得を目指す大学院生」にとって、ちょうどよいトレーニングである修論を省略するというのは奇妙におもえてくる。
そう読むと、この提案は結果的に「修士」の資格を広く、容易にとらせるためのもののように思える。ではそれは何のため、誰のためなのだろうか?そしてそれによってどのような未来が予想できるのだろうか。
この辺の関連記事がいろいろと考えさせてくれる。
http://d.hatena.ne.jp/next49/20110201
http://kentapb.blog27.fc2.com/blog-entry-2195.html
中央教育審議会
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/index.htm
※中央教育審議会の提言はしばしば個々の大学内の制度改革案や、概算要求などの際に参照されることがおおい(らしい)。そういう意味で数年後の大学、大学院の姿をうらなう上で注目されるものである。
http://www.nikkei.com/news/headline/article/g=96958A9C93819695E0E4E2E6EB8DE0E4E3E2E0E2E3E39180EAE2E2E2
「広い視野と能力を持った人材を育てるのが狙い。従来の修士課程は論文作成のため早い段階から特定の研究室に所属して研究テーマを絞ることが多く、博士課程を終えても産業界から「専門分野には詳しいが応用が利かず、使いにくい」と評価されてきた。」(日本経済新聞 2011/10/26)
「広い視野と能力」はペーパー試験と面接で評価できるという理解らしい。海外の大学院などに「部分的」にならった制度なのかもしれないが、形だけの試験のようなものになってしまう可能性もあろう。そもそもその新制度を運用するのはそれまで別の方法を主導してきた教員なのだから。
一方、論文作成指導の過程でしか養えないような個人的探求心や分析力、叙述力といった能力もあるはずだが、それを身につけたものがかりに「専門分野には詳しいが応用が利かず、使いにくい」人材となってしまうのだとして、その原因はやはり修士論文という審査方法にあるといえるのだろうか。論文を指導する側に問題があったり、受け皿となる産業界にこそそうした能力を引き出す応用力を補填する必要はないのだろうか。
この提案(方針)は 「博士号取得を目指す大学院生が主な対象」だそうだが、博士論文までを免除する気はないようである。それなのに 「博士号取得を目指す大学院生」にとって、ちょうどよいトレーニングである修論を省略するというのは奇妙におもえてくる。
そう読むと、この提案は結果的に「修士」の資格を広く、容易にとらせるためのもののように思える。ではそれは何のため、誰のためなのだろうか?そしてそれによってどのような未来が予想できるのだろうか。
この辺の関連記事がいろいろと考えさせてくれる。
http://d.hatena.ne.jp/next49/20110201
http://kentapb.blog27.fc2.com/blog-entry-2195.html
中央教育審議会
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/index.htm
※中央教育審議会の提言はしばしば個々の大学内の制度改革案や、概算要求などの際に参照されることがおおい(らしい)。そういう意味で数年後の大学、大学院の姿をうらなう上で注目されるものである。
拝受 敦煌出土のウイグル語暦占文書・西魏北魏の二四軍と府兵制 ― 2011/10/27 02:17
松井太、敦煌出土のウイグル語暦占文書、『人文社會論叢』(弘前大学)第26号、2011年8月。
平田陽一郎、西魏北魏の二四軍と府兵制 、『東洋史研究』第70巻2号、2011年9月。
松井先生と平田先生から抜き刷りをいただいた。ありがとうございました。
ともに大変おもしろい論文で紹介済み。
http://iwamoto.asablo.jp/blog/2011/09/20/6108494
http://iwamoto.asablo.jp/blog/2011/10/14/6157023
これは何か、これは本当か、素朴な疑問や興味をもつことがある。そしてそれがなぜかわかったとき、ものすごく驚いたりうれしかったりするわけだが、そういう知的快感を得られる技術や技法があるならば、それはそれだけでこの世に存在する価値があるといえるだろう。そしてそれを他人に伝えるにはその考え方の過程を披露する以外の方法はない。
平田陽一郎、西魏北魏の二四軍と府兵制 、『東洋史研究』第70巻2号、2011年9月。
松井先生と平田先生から抜き刷りをいただいた。ありがとうございました。
ともに大変おもしろい論文で紹介済み。
http://iwamoto.asablo.jp/blog/2011/09/20/6108494
http://iwamoto.asablo.jp/blog/2011/10/14/6157023
これは何か、これは本当か、素朴な疑問や興味をもつことがある。そしてそれがなぜかわかったとき、ものすごく驚いたりうれしかったりするわけだが、そういう知的快感を得られる技術や技法があるならば、それはそれだけでこの世に存在する価値があるといえるだろう。そしてそれを他人に伝えるにはその考え方の過程を披露する以外の方法はない。
拝受 カフカハ遺跡群の図面と出土品(土器と木彫) ― 2011/10/27 17:17
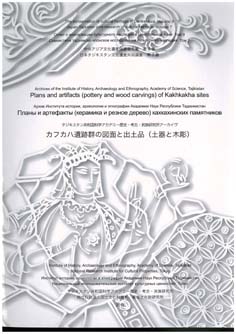
山内和也・サイドムロド=ボボムロエフ(編)『カフカハ遺跡群の図面と出土品(土器と木彫)』(中央アジア文化遺産保護報告集第9巻・日本タジキスタン文化遺産共同調査第7巻)、タジキスタン共和国科学アカデミー・東京文化財研究所、2011年6月。
国立文化財機構・東京文化財研究所からいただいた。ありがとうございました。
タジキスタン共和国北部、シャフリスタン村近辺の5-9世紀のソグド文化圏のカライ・カフカハI,II遺跡およびチリフジラ遺跡に関する図面および出土資料に関する報告。この地はタシケントとサマルカンドの間に位置し、玄奘が通過した場所でもあるとのこと。この号はほとんどが図面とスケッチである。
なお、同じ遺跡群の報告書として以下のようなものがすでに公刊されている。
『カフカハ遺跡群出土壁画』
http://iwamoto.asablo.jp/blog/2010/12/13/5579357
タジキスタン共和国北部、シャフリスタン村のイメージをネットで探すと以下のサイトに行き当たった。カライ・カフカハ遺跡の写真もある。
http://oribito.sakura.ne.jp/cn51/tajikistan.c.html
(染織の専門家の方のホームページ)
国立文化財機構・東京文化財研究所からいただいた。ありがとうございました。
タジキスタン共和国北部、シャフリスタン村近辺の5-9世紀のソグド文化圏のカライ・カフカハI,II遺跡およびチリフジラ遺跡に関する図面および出土資料に関する報告。この地はタシケントとサマルカンドの間に位置し、玄奘が通過した場所でもあるとのこと。この号はほとんどが図面とスケッチである。
なお、同じ遺跡群の報告書として以下のようなものがすでに公刊されている。
『カフカハ遺跡群出土壁画』
http://iwamoto.asablo.jp/blog/2010/12/13/5579357
タジキスタン共和国北部、シャフリスタン村のイメージをネットで探すと以下のサイトに行き当たった。カライ・カフカハ遺跡の写真もある。
http://oribito.sakura.ne.jp/cn51/tajikistan.c.html
(染織の専門家の方のホームページ)