新収 漢文と東アジア 他 ― 2010/10/22 21:35
金文京(著)『漢文と東アジア―訓読の文化圏』(岩波新書)、岩波書店、2010年8月
加地伸行(著)『漢文法基礎―本当にわかる漢文入門』(講談社学術文庫)講談社、2010年10月
吉川忠夫・船山徹(訳)『高僧伝』(4)(岩波文庫)、岩波書店、2010年9月
藤堂明保・竹田晃・影山輝國(訳注)『倭国伝』(講談社学術文庫)、講談社、2010年9月
山本忠尚(著)『高松塚・キトラ古墳の謎』吉川弘文館、2010年10月
榎本渉(著)『僧侶と海商たちの東シナ海』(講談社撰書メチエ)、講談社、2010年10月
林淳(著)『天文方と陰陽道』(日本史リブレット)、山川出版社、2006年
ここ数ヶ月に購入した新書、文庫本など。いずれもWeb上には情報がたくさんある。
上から4冊目までは訓読、翻訳の技術を学ぶ際に参考になる点が少なくない。学生に紹介したり、回読用に購入したものもある。漢文法基礎は読みやすく得るところが少なくないので漢文訓読がはじめての学生にはよさそう。少々冗長。『漢文と東アジア』は間口は狭いのに実はすごい奥行きがある店のようで、自分には得るところが多いが、学部生には少々、きつそう。
いずれの本も蘊蓄が深くて購入したはよいが、肝心な部分を吸収するには読書の時間がない。
『高僧伝』『漢文と東アジア』『倭国伝』『高松塚・キトラ古墳』に北朝関係の記事がある。
加地伸行(著)『漢文法基礎―本当にわかる漢文入門』(講談社学術文庫)講談社、2010年10月
吉川忠夫・船山徹(訳)『高僧伝』(4)(岩波文庫)、岩波書店、2010年9月
藤堂明保・竹田晃・影山輝國(訳注)『倭国伝』(講談社学術文庫)、講談社、2010年9月
山本忠尚(著)『高松塚・キトラ古墳の謎』吉川弘文館、2010年10月
榎本渉(著)『僧侶と海商たちの東シナ海』(講談社撰書メチエ)、講談社、2010年10月
林淳(著)『天文方と陰陽道』(日本史リブレット)、山川出版社、2006年
ここ数ヶ月に購入した新書、文庫本など。いずれもWeb上には情報がたくさんある。
上から4冊目までは訓読、翻訳の技術を学ぶ際に参考になる点が少なくない。学生に紹介したり、回読用に購入したものもある。漢文法基礎は読みやすく得るところが少なくないので漢文訓読がはじめての学生にはよさそう。少々冗長。『漢文と東アジア』は間口は狭いのに実はすごい奥行きがある店のようで、自分には得るところが多いが、学部生には少々、きつそう。
いずれの本も蘊蓄が深くて購入したはよいが、肝心な部分を吸収するには読書の時間がない。
『高僧伝』『漢文と東アジア』『倭国伝』『高松塚・キトラ古墳』に北朝関係の記事がある。
新収 書誌学のすすめ ― 2010/10/07 22:02
高橋智(著)『書誌学のすすめ―中国の愛書文化に学ぶ』、東方書店、2010年9月。
中国書誌学の入門書。基本的なことがおさえてあって勉強になる。
これまで何本か論文を書いてきたが、書誌学用語を間違えていて、いろいろ・・・あった(他にも・・・・おもいださないことにする)。間違いを気にしすぎると論文が書けなくなる。
例えばフランス語や英語の解説では、胡蝶装(Butterfly ~)に相当する語彙で解説されているのに、日本ではその装丁は粘葉装とよばないととか、けっこうややこしい(同義であるとする解説もありますけどね)。まあ、間違えると意味が通じなくなるのでまずいわけだが、専門用語は学習すればよい。
「書誌学はけしてすすめられようなものではない」という抑えめな言葉がいい。
実際、実物の本を見るのはものすごくおもしろいが、これにはまると歴史学はできなくなる。あなたが大図書館の専属でないなら、その分野はやめといたほうがいい、書誌学はエリート(研究者の中のエリートってことですな)だけがやるものだ、と学生時代いわれたことがある。
学習するべきだが、研究分野にはしないほうがいいという意味だと理解している。
中国書誌学の入門書。基本的なことがおさえてあって勉強になる。
これまで何本か論文を書いてきたが、書誌学用語を間違えていて、いろいろ・・・あった(他にも・・・・おもいださないことにする)。間違いを気にしすぎると論文が書けなくなる。
例えばフランス語や英語の解説では、胡蝶装(Butterfly ~)に相当する語彙で解説されているのに、日本ではその装丁は粘葉装とよばないととか、けっこうややこしい(同義であるとする解説もありますけどね)。まあ、間違えると意味が通じなくなるのでまずいわけだが、専門用語は学習すればよい。
「書誌学はけしてすすめられようなものではない」という抑えめな言葉がいい。
実際、実物の本を見るのはものすごくおもしろいが、これにはまると歴史学はできなくなる。あなたが大図書館の専属でないなら、その分野はやめといたほうがいい、書誌学はエリート(研究者の中のエリートってことですな)だけがやるものだ、と学生時代いわれたことがある。
学習するべきだが、研究分野にはしないほうがいいという意味だと理解している。
拝受 聞いて楽しむ菜根譚 ― 2010/08/26 18:42
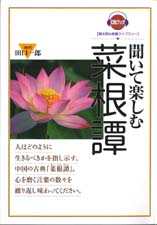
田口一郎(著)『聞いて楽しむ菜根譚』創元社、2010年6月
田口先生からいただいた。ありがとうございました。
特に含蓄のある58条を選んで、書き下し、訳、原文、注を示す。一般向きの内容。
裏表紙に
「夜眠れない、早朝に目覚めて所在ない、
体力、視力が落ちて読書ができない、
癒しを求める中高世代に。」とある
(このほか、自分磨きを望む現役世代に、というのもあるが)。
「夜眠れないので、早朝に目覚めることなく所在ない」ことを除けば、当てはまりつつあるかも。ただ、少子高齢化がすすんでいるので、自分くらいでは中高世代に入れてもらえないであろうが。
田口先生からいただいた。ありがとうございました。
特に含蓄のある58条を選んで、書き下し、訳、原文、注を示す。一般向きの内容。
裏表紙に
「夜眠れない、早朝に目覚めて所在ない、
体力、視力が落ちて読書ができない、
癒しを求める中高世代に。」とある
(このほか、自分磨きを望む現役世代に、というのもあるが)。
「夜眠れないので、早朝に目覚めることなく所在ない」ことを除けば、当てはまりつつあるかも。ただ、少子高齢化がすすんでいるので、自分くらいでは中高世代に入れてもらえないであろうが。
新収 史学雑誌 第119編第7号 ほか ― 2010/08/18 18:59
『史学雑誌』第119編第7号、2010年7月
梶山智史、屠本『十六国春秋』考-明代における五胡十六国史研究の一斑
『東方学』第120輯、2010年7月
中嶋隆蔵、隋唐以前における「静坐」
柿沼陽平、晋代貨幣経済の構造とその特質
江川式部、唐代の上墓儀礼―墓祭習俗の礼典編入とその意義について―
Barend J.ter HAAR(著)丸山宏(訳)、書物を読み利用する歴史―新しい史料から―
梶山論文の屠本とは万暦37年(1609)に屠喬孫を中心として編纂刊行された『十六国春秋』のこと。
梶山智史、屠本『十六国春秋』考-明代における五胡十六国史研究の一斑
『東方学』第120輯、2010年7月
中嶋隆蔵、隋唐以前における「静坐」
柿沼陽平、晋代貨幣経済の構造とその特質
江川式部、唐代の上墓儀礼―墓祭習俗の礼典編入とその意義について―
Barend J.ter HAAR(著)丸山宏(訳)、書物を読み利用する歴史―新しい史料から―
梶山論文の屠本とは万暦37年(1609)に屠喬孫を中心として編纂刊行された『十六国春秋』のこと。
拝受 『羅氏雪堂蔵書遺珍』所収「経世大典輯本」について ― 2010/06/30 21:32
渡辺健哉、『羅氏雪堂蔵書遺珍』所収「経世大典輯本」について、『集刊東洋学』第103号、2010年5月。
渡辺健哉、元の大都における中央官庁の建設について、『九州大学 東洋史論集』第38号、2010年4月。
渡辺健哉さんからいただいた。ありがとうございました。
前者。羅振玉所蔵の「経世大典輯本」について、先行研究で論じきれていない「来歴について可能限り追跡」、「「大典輯本」に含まれる文章についても、それが元代史を解明するにあたって、どういった点で有効性を持つか」(はじめに、より)という視点から解説を加えたもの。
渡辺健哉、元の大都における中央官庁の建設について、『九州大学 東洋史論集』第38号、2010年4月。
渡辺健哉さんからいただいた。ありがとうございました。
前者。羅振玉所蔵の「経世大典輯本」について、先行研究で論じきれていない「来歴について可能限り追跡」、「「大典輯本」に含まれる文章についても、それが元代史を解明するにあたって、どういった点で有効性を持つか」(はじめに、より)という視点から解説を加えたもの。
拙稿 東条琴台旧蔵『君公御蔵目録』小考―高田藩榊原家の資料群の変遷に関連して ― 2010/06/13 02:31
岩本篤志「東条琴台旧蔵『君公御蔵目録』小考―高田藩榊原家の資料群の変遷に関連して」(『汲古』,第57号, 65~72頁、2010年6月)
国内の多くの旧藩資料は明治期に散逸し、残存していても本来どのような管理をされていたのか十分に明らかにできない場合が少なくない。
高田藩および榊原家もその例に漏れず、明治期に各所に分蔵され、運悪く焼失、散逸したものもあったようである。現存が確認されている資料としては、明治三年の藩庁火災をまぬがれ、残存した藩庁文書と旧藩士家および榊原家伝来のものとが榊神社に献納されて原型が形作られた高田図書館所蔵「榊原文書」および、似た経緯をもつ旧蔵書をあわせた図書館系資料群、そして現在、上越市立総合博物館に寄託され、二〇〇九年に目録が刊行された「榊原家史料」の二つが主要なものとみられる 。
ともに整理と研究がすすめられており、近年では近世の現用秩序の復原を意図した所謂「史料学的」試みがはかられている 。ただ既知の史料には高田移封後の資料秩序を示す目録を欠いており、その全貌や管理状況を知るには限界があった。
(中略)
調べるうちに管見の限り先行研究には言及がないものの、この目録はたしかに東条琴台旧蔵の高田藩榊原家の御蔵目録で、高田移封後の榊原家の資料群の構成をあきらかにする史料となると考えるに至った。(「はじめに」より)
国内の多くの旧藩資料は明治期に散逸し、残存していても本来どのような管理をされていたのか十分に明らかにできない場合が少なくない。
高田藩および榊原家もその例に漏れず、明治期に各所に分蔵され、運悪く焼失、散逸したものもあったようである。現存が確認されている資料としては、明治三年の藩庁火災をまぬがれ、残存した藩庁文書と旧藩士家および榊原家伝来のものとが榊神社に献納されて原型が形作られた高田図書館所蔵「榊原文書」および、似た経緯をもつ旧蔵書をあわせた図書館系資料群、そして現在、上越市立総合博物館に寄託され、二〇〇九年に目録が刊行された「榊原家史料」の二つが主要なものとみられる 。
ともに整理と研究がすすめられており、近年では近世の現用秩序の復原を意図した所謂「史料学的」試みがはかられている 。ただ既知の史料には高田移封後の資料秩序を示す目録を欠いており、その全貌や管理状況を知るには限界があった。
(中略)
調べるうちに管見の限り先行研究には言及がないものの、この目録はたしかに東条琴台旧蔵の高田藩榊原家の御蔵目録で、高田移封後の榊原家の資料群の構成をあきらかにする史料となると考えるに至った。(「はじめに」より)
新収 明治前期日中学術交流の研究 ― 2010/06/01 21:20
陳捷(著)『明治前期日中学術交流の研究』汲古書院、2003年2月。
以前から何度も図書館で開き、どうせだから購入しようと思っていたが、他の本を優先していて未入手だった。
日本に中国の古籍がたくさんあるが、中国や台湾にも日本で出版された古籍・善本がたくさんある。その経緯を調べていく際に本書は良いガイドになる。そこは米沢藩の宮島誠一郎や日本公使であった李盛鐸が行き交う場である。
本書は古書で入手した。日中学術史にその名を知られ、数年前に物故された先生の蔵書印が捺され、ところどころ線が引かれている。
以前から何度も図書館で開き、どうせだから購入しようと思っていたが、他の本を優先していて未入手だった。
日本に中国の古籍がたくさんあるが、中国や台湾にも日本で出版された古籍・善本がたくさんある。その経緯を調べていく際に本書は良いガイドになる。そこは米沢藩の宮島誠一郎や日本公使であった李盛鐸が行き交う場である。
本書は古書で入手した。日中学術史にその名を知られ、数年前に物故された先生の蔵書印が捺され、ところどころ線が引かれている。
拝受 『令義解』「上令義解表」の注釈所引『論語義疏』の性格について ― 2010/05/26 18:06
高田宗平、『令義解』「上令義解表」の注釈所引『論語義疏』の性格について、『日本漢文学研究』 第5号、2010年3月。
高田さんからいただいた。ありがとうございました。タイトルの通り、注に引用された典籍の文章から、その性格を探っている。
前稿では敦煌本等を使用しておられたが、ここでは新潟の市島酒造の史料館所蔵本(!)などにも言及されている。ありがとうございました。
市島酒造
http://www.ichishima.jp/oumon/tenji/index.html
高田さんからいただいた。ありがとうございました。タイトルの通り、注に引用された典籍の文章から、その性格を探っている。
前稿では敦煌本等を使用しておられたが、ここでは新潟の市島酒造の史料館所蔵本(!)などにも言及されている。ありがとうございました。
市島酒造
http://www.ichishima.jp/oumon/tenji/index.html
拝受 唐僧法進撰『梵網経注』の史料的意義 ― 2010/05/08 01:54
東野治之、唐僧法進撰『梵網経注』の史料的意義、『佛教文学』第34号、2010年3月。
東野先生からいただいた。ありがとうございました。
佛教文献に関する内容で、主に法進の注釈の手法からどのような典籍(類書など)に依拠したのかを読み取っている。南北朝隋唐期の文献や遊戯関係史料におよぶ。
東野先生からいただいた。ありがとうございました。
佛教文献に関する内容で、主に法進の注釈の手法からどのような典籍(類書など)に依拠したのかを読み取っている。南北朝隋唐期の文献や遊戯関係史料におよぶ。
拝受 吐魯番本『爾雅注』について ― 2010/04/25 21:54
張娜麗、吐魯番本『爾雅注』について、『敦煌・吐魯番出土漢文文書の新研究』、2009年3月。
張先生からいただいた。ありがとうございました。
結論を四点に集約されているが、私の関心からいえば最初の一点がとくに重要に思えた。
「吐魯番本は、その遺存している部分からすれば、・・・・こうした形態は吐魯番本がテキストそのものの姿をより正確に写し記すということから起こされたのではなく、一種の識字練習のために随意にテキストを写し記す中から起こされたものであることを証すようにおもわれる」(原文正字)
張先生からいただいた。ありがとうございました。
結論を四点に集約されているが、私の関心からいえば最初の一点がとくに重要に思えた。
「吐魯番本は、その遺存している部分からすれば、・・・・こうした形態は吐魯番本がテキストそのものの姿をより正確に写し記すということから起こされたのではなく、一種の識字練習のために随意にテキストを写し記す中から起こされたものであることを証すようにおもわれる」(原文正字)