拝受 アジナ・テパ仏教寺院考古学調査報告 ほか ― 2011/06/02 17:37

東京文化財研究所文化遺産国際協力センター/タジキスタン共和国歴史・考古・民族研究所(山内和也編集)『アジナ・テパ仏教寺院考古学調査報告(2006~2008年)』(中央アジア文化遺産保護報告集第7巻・日本タジキスタン文化遺産共同調査第5巻)、東京文化財研究所、2011年1月。
東京文化財研究所文化遺産国際協力センター/タジキスタン共和国歴史・考古・民族研究所(編)『カフカハ遺跡群出土壁画』(中央アジア文化遺産保護報告集第6巻、日本タジキスタン文化遺産共同調査第4巻)、東京文化財研究所、2010年9月。
東京文化財研究所からいただいた。ありがとうございました。いただいてから一ヶ月以上がすぎた。後者は別ルートでもいただいていて以前紹介済み。
http://iwamoto.asablo.jp/blog/2010/12/13/5579357
前者、アジナ・テパの遺跡は7~8世紀のものとされる。表紙写真のとおり、印影のある大甕の破片が出土している。解説によると、数多く出土した甕片のうちこの一点(二顆)だけが確認されたという。また、これら印影を指輪印章を捺したものとみて、図像の分析をおこなっているが何をあらわすかは不明とする。たしかに興味深い。
東京文化財研究所文化遺産国際協力センター/タジキスタン共和国歴史・考古・民族研究所(編)『カフカハ遺跡群出土壁画』(中央アジア文化遺産保護報告集第6巻、日本タジキスタン文化遺産共同調査第4巻)、東京文化財研究所、2010年9月。
東京文化財研究所からいただいた。ありがとうございました。いただいてから一ヶ月以上がすぎた。後者は別ルートでもいただいていて以前紹介済み。
http://iwamoto.asablo.jp/blog/2010/12/13/5579357
前者、アジナ・テパの遺跡は7~8世紀のものとされる。表紙写真のとおり、印影のある大甕の破片が出土している。解説によると、数多く出土した甕片のうちこの一点(二顆)だけが確認されたという。また、これら印影を指輪印章を捺したものとみて、図像の分析をおこなっているが何をあらわすかは不明とする。たしかに興味深い。
拝受 アジアが結ぶ東西世界 ほか ― 2011/05/20 17:54

橋寺知子、森部豊、 蜷川順子、新谷英治(共編)『アジアが結ぶ東西世界』(アジアにおける経済・法・文化の展開と交流)関西大学出版部、2011年3月。
栄新江、森部豊(訳・解説)「新出石刻史料から見たソグド人研究の動向」『関西大学東西学術研究所紀要』第44輯、2011年4月。
森部先生、栄新江先生からいただいた。ありがとうございました。
ともにいただいて半月以上が経っておりますがあらためて感謝。
前者の目次は以下のとおり。第1部は講演録のかたちで第2部は論文になっている。
第1部 関西大学3研究所公開合同シンポジウム「アジアが結ぶ東西世界」
栄新江、イスラーム化以前の中央アジア―東西交渉史上の役割
宮紀子、全真教からみたモンゴル時代の東西交流―和算の来た道
Arindam Dutta、デルタと神々―帝国のピクチャレスクという景観
羽田正、インド洋海域世界とイスラーム
第2部 論集「アジアが結ぶ東西世界」
栄新江、イスラーム化以前の中央アジア―東西交渉史上の役割
森部豊、東ユーラシア世界におけるソグド人の外交活動に関する覚書
福田浩子、中央アジア・トルクメン人の民族衣装コイネクについて
Arindam Dutta、デルタと神々―帝国のピクチャレスクという景観
橋寺知子、インドにおける近代建築-伝統とモダニズム
新谷英治、『キターブ・バフリエ』韻文序に見えるインド洋
http://bookweb.kinokuniya.co.jp/htm/4873545226.html
後者は近年公刊された石刻史料集を精査、あらかた解説を加えているほか、どのようにソグド人の墓誌と判断するかなども記されており、必見の論文といえる。
実は森部先生のはからいでここに扱われている資料の写真または実物をみせていただく機会も得た。なかなかたいしたものでした。
栄新江、森部豊(訳・解説)「新出石刻史料から見たソグド人研究の動向」『関西大学東西学術研究所紀要』第44輯、2011年4月。
森部先生、栄新江先生からいただいた。ありがとうございました。
ともにいただいて半月以上が経っておりますがあらためて感謝。
前者の目次は以下のとおり。第1部は講演録のかたちで第2部は論文になっている。
第1部 関西大学3研究所公開合同シンポジウム「アジアが結ぶ東西世界」
栄新江、イスラーム化以前の中央アジア―東西交渉史上の役割
宮紀子、全真教からみたモンゴル時代の東西交流―和算の来た道
Arindam Dutta、デルタと神々―帝国のピクチャレスクという景観
羽田正、インド洋海域世界とイスラーム
第2部 論集「アジアが結ぶ東西世界」
栄新江、イスラーム化以前の中央アジア―東西交渉史上の役割
森部豊、東ユーラシア世界におけるソグド人の外交活動に関する覚書
福田浩子、中央アジア・トルクメン人の民族衣装コイネクについて
Arindam Dutta、デルタと神々―帝国のピクチャレスクという景観
橋寺知子、インドにおける近代建築-伝統とモダニズム
新谷英治、『キターブ・バフリエ』韻文序に見えるインド洋
http://bookweb.kinokuniya.co.jp/htm/4873545226.html
後者は近年公刊された石刻史料集を精査、あらかた解説を加えているほか、どのようにソグド人の墓誌と判断するかなども記されており、必見の論文といえる。
実は森部先生のはからいでここに扱われている資料の写真または実物をみせていただく機会も得た。なかなかたいしたものでした。
新収 Iskusstvo Sogda ― 2011/02/28 19:49

Б. И. Маршак," Искусство Согда", Государственный Эрмитаж,Санкт-Петербург,2009.2
B.I.マルシャーク監修、エルミタージュ美術館刊行のブックレットサイズのガイド『ソグドの芸術』。フルカラーの写真多数。エルミタージュ美術館にはソ連時代に中央アジア発掘で収集された遺物が多数展示されている。このブックレットでは主に壁画の解説がなされている。なお、ソグド美術の大家マルシャークは2006年に逝去している。
お土産に買ってくれば喜ばれたであろうが、店頭に一冊しかなかった。
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4886710/
B.I.マルシャーク監修、エルミタージュ美術館刊行のブックレットサイズのガイド『ソグドの芸術』。フルカラーの写真多数。エルミタージュ美術館にはソ連時代に中央アジア発掘で収集された遺物が多数展示されている。このブックレットでは主に壁画の解説がなされている。なお、ソグド美術の大家マルシャークは2006年に逝去している。
お土産に買ってくれば喜ばれたであろうが、店頭に一冊しかなかった。
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4886710/
新収 ソグド人の美術と言語 ― 2011/02/28 19:05
曽布川寛・吉田豊(編)『ソグド人の美術と言語』、臨川書店、2011年2月。
出版社のページ
http://www.rinsen.com/linkbooks/ISBN978-4-653-04049-1.htm
第1章 ソグド人とソグドの歴史 (吉田豊)
第2章 ソグド人の壁画 (影山悦子)
第3章 ソグド人の言語 (吉田豊)
第4章 中国文化におけるソグドとその銀器 (斉東方 /訳:古田真一)
第5章 中国出土ソグド石刻画像の図像学 (曽布川寛)
昨年末頃だろうか、出るぞという噂を聞いて、まもなくホームページに広告はみつけたが、その後、刊行が遅れていった印象だった。そして2月末に刊行、入手できた。
題名に「ソグド人」と名付けられたもの自体少ないが、ソグド人の言語や壁画について日本語で分析をしめしたものも限られている。その意味でこれからの研究の基準となるような一冊。
出版社のページ
http://www.rinsen.com/linkbooks/ISBN978-4-653-04049-1.htm
第1章 ソグド人とソグドの歴史 (吉田豊)
第2章 ソグド人の壁画 (影山悦子)
第3章 ソグド人の言語 (吉田豊)
第4章 中国文化におけるソグドとその銀器 (斉東方 /訳:古田真一)
第5章 中国出土ソグド石刻画像の図像学 (曽布川寛)
昨年末頃だろうか、出るぞという噂を聞いて、まもなくホームページに広告はみつけたが、その後、刊行が遅れていった印象だった。そして2月末に刊行、入手できた。
題名に「ソグド人」と名付けられたもの自体少ないが、ソグド人の言語や壁画について日本語で分析をしめしたものも限られている。その意味でこれからの研究の基準となるような一冊。
拝受 東西交渉とイラン文化 ― 2011/02/12 00:19
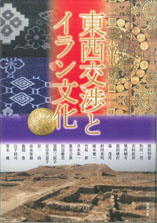
井本英一(編)『東西交渉とイラン文化』(アジア遊学 137)、勉誠出版、2010年12月
執筆者の森部豊先生と山下将司先生からいただいた。ありがとうございました。ユーラシア大陸をまたぐ豪華な執筆陣。
井本英一、はじめに―東西交渉とイラン文化
井本英一、ミトラ信仰の東西
岡田明憲、世界精神史におけるゾロアスター教―宗教思想の文化交渉面を中心に
松村一男、(コラム)アナーヒター女神の東西
吉田敦彦、(コラム)アーサー王伝説に見られる、スキュタイ神話との顕著な類似
奥西峻介、四ツ目の犬・四ツ白の犬
前田耕作、ヘレノ・イラニズムと仏教の交流
森茂男、大乗仏教に入ったイラン文化的要素―阿弥陀仏と極楽をめぐって
杉田英明、佛教説話「井戸のなかの男」の西方伝播 ―ペルシア文字の貢献を中心に
岡本健一、(コラム)アレクサンダー伝説の東漸
竹原新、イランのこぶとりじいさんとその背景
井本英一、元型、複合、伝播
森谷公俊、アレクサンドロスの東征軍とペルシア文化
田辺勝美、ササン銀器から見た東西文化交流―獅子と虎の描写をめぐって
道明三保子、東西交流におけるイラン染織―連珠円文錦の系譜
星谷美恵子、(コラム)花菱の文様にみる東西交流―イラン織物と絵絣の関連から
谷一尚、サーサーン朝ペルシア・ガラスの「直」(中国・東方流入)と「風」(中国・東方化)
由水常雄、(コラム)工芸分野からみた古代イランの文化交流
森部豊、ソグド人の東方進出とその活動―商業活動と外交活動を中心に
山下将司、隋唐の建国と中国在住ソグド人
青木健、パールスィーの中国・日本来航―近現代の極東ゾロアスター教文化
執筆者の森部豊先生と山下将司先生からいただいた。ありがとうございました。ユーラシア大陸をまたぐ豪華な執筆陣。
井本英一、はじめに―東西交渉とイラン文化
井本英一、ミトラ信仰の東西
岡田明憲、世界精神史におけるゾロアスター教―宗教思想の文化交渉面を中心に
松村一男、(コラム)アナーヒター女神の東西
吉田敦彦、(コラム)アーサー王伝説に見られる、スキュタイ神話との顕著な類似
奥西峻介、四ツ目の犬・四ツ白の犬
前田耕作、ヘレノ・イラニズムと仏教の交流
森茂男、大乗仏教に入ったイラン文化的要素―阿弥陀仏と極楽をめぐって
杉田英明、佛教説話「井戸のなかの男」の西方伝播 ―ペルシア文字の貢献を中心に
岡本健一、(コラム)アレクサンダー伝説の東漸
竹原新、イランのこぶとりじいさんとその背景
井本英一、元型、複合、伝播
森谷公俊、アレクサンドロスの東征軍とペルシア文化
田辺勝美、ササン銀器から見た東西文化交流―獅子と虎の描写をめぐって
道明三保子、東西交流におけるイラン染織―連珠円文錦の系譜
星谷美恵子、(コラム)花菱の文様にみる東西交流―イラン織物と絵絣の関連から
谷一尚、サーサーン朝ペルシア・ガラスの「直」(中国・東方流入)と「風」(中国・東方化)
由水常雄、(コラム)工芸分野からみた古代イランの文化交流
森部豊、ソグド人の東方進出とその活動―商業活動と外交活動を中心に
山下将司、隋唐の建国と中国在住ソグド人
青木健、パールスィーの中国・日本来航―近現代の極東ゾロアスター教文化
新収 新アジア仏教史05中央アジア―文明・文化の交差点 ― 2010/12/16 21:53
奈良康明・石井公成(編)『新アジア仏教史05中央アジア―文明・文化の交差点』佼成出版社、2010年10月。
脱稿後の著者の先生お一人の発表を拝聴させていただく機会があり、まもなく購入。
シリーズ一覧と目次はこちら。Flashになっている。
http://www.kosei-shuppan.co.jp/ajibutsu/overview/
第1章 インダス越えて―仏教の中央アジア (山田明爾)
第2章 東トルキスタンにおける仏教の受容とその展開 (橘堂晃一)
第3章 中央アジアの仏教写本 (松田和信)
第4章 出土資料が語る宗教文化―イラン語圏の仏教を中心に― (吉田豊)
第5章 中央アジアの仏教美術 (宮治昭)
第6章 仏教信仰と社会 (蓮池利隆・山部能宜)
第7章 敦煌―文献・文化・美術 (沖本克己・川崎ミチコ・濱田瑞美)
このほかコラムが六点(シルクロードと仏教と楽器、略奪と文化財保護、スウェン・ヘディンの軌跡、西夏文字、日本の西域調査、辺境詩の伝統ー西域を詠じた漢詩)。第4章はソグド、ゾロアスター教、マニ教、キリスト教(景教)研究に関わる内容。
このシリーズは1970年代刊行の『アジア仏教史』の新版として刊行されており、解説によると、この巻は「中国編5 シルクロードの宗教」の後継に位置づけられるようである。
そのほか1980年代半ばには『講座敦煌8 敦煌仏典と禅』、『講座敦煌 6 敦煌胡語文献』が刊行されているが、それ以後、どういった資料が発見、解読され、研究がどのように進展したのかを把握できる内容になっている。
すでにいろんなサイトで紹介されているようだ。胡語文献ブームが来る(来ている?)のだろうか。・・・
脱稿後の著者の先生お一人の発表を拝聴させていただく機会があり、まもなく購入。
シリーズ一覧と目次はこちら。Flashになっている。
http://www.kosei-shuppan.co.jp/ajibutsu/overview/
第1章 インダス越えて―仏教の中央アジア (山田明爾)
第2章 東トルキスタンにおける仏教の受容とその展開 (橘堂晃一)
第3章 中央アジアの仏教写本 (松田和信)
第4章 出土資料が語る宗教文化―イラン語圏の仏教を中心に― (吉田豊)
第5章 中央アジアの仏教美術 (宮治昭)
第6章 仏教信仰と社会 (蓮池利隆・山部能宜)
第7章 敦煌―文献・文化・美術 (沖本克己・川崎ミチコ・濱田瑞美)
このほかコラムが六点(シルクロードと仏教と楽器、略奪と文化財保護、スウェン・ヘディンの軌跡、西夏文字、日本の西域調査、辺境詩の伝統ー西域を詠じた漢詩)。第4章はソグド、ゾロアスター教、マニ教、キリスト教(景教)研究に関わる内容。
このシリーズは1970年代刊行の『アジア仏教史』の新版として刊行されており、解説によると、この巻は「中国編5 シルクロードの宗教」の後継に位置づけられるようである。
そのほか1980年代半ばには『講座敦煌8 敦煌仏典と禅』、『講座敦煌 6 敦煌胡語文献』が刊行されているが、それ以後、どういった資料が発見、解読され、研究がどのように進展したのかを把握できる内容になっている。
すでにいろんなサイトで紹介されているようだ。胡語文献ブームが来る(来ている?)のだろうか。・・・
拝受 環境と歴史学 ― 2010/11/01 21:08
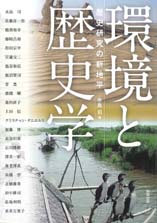
水島司(編)『環境と歴史学―歴史研究の新地平』、勉誠出版、2010年9月。
執筆者の一人の森田さんからいただいた。ありがとうございました。
歴史学研究において総合的で新らしいテーマである「環境」という切り口からの論考を集め、その展望をしめしたもの。
森田直子、ドイツの歴史学と「環境史」―ヨアヒム・ラートカウ『自然と権力―環境の世界史』を例に
全部の目次はこちら。
http://www.bensey.co.jp/book/2272.html
以下は眼を通したもの。とりあえずはアジア系に片寄る。
鶴間和幸、歴史学と自然科学ー始皇帝陵の自然環境の復元
卯田宗平、中国における環境史研究の可能性―生業技術からみるミクロな人間ー環境系
上田信、生態環境史の視点による地域史の再構築―生物多様性の歴史的変化研究のための史料について
クリスチャン・ダニエルズ、雲南地域住民の天然資源保護・管理―十八世紀後半~19世紀前半の元江流域・メコン河上流域を事例として
石川博樹、偽バナナは消えたのか―北部エチオピアの栽培植物をめぐる歴史学的考察
海老澤衷、棚田と水資源を活用した楠木正成
高橋 学、環境史からみた中世の開始と終焉
北條勝貴、神仏習合と自然環境―言説・心性・実体
それぞれの切り口がおもしろいのであとで精読することにしたい。
執筆者の一人の森田さんからいただいた。ありがとうございました。
歴史学研究において総合的で新らしいテーマである「環境」という切り口からの論考を集め、その展望をしめしたもの。
森田直子、ドイツの歴史学と「環境史」―ヨアヒム・ラートカウ『自然と権力―環境の世界史』を例に
全部の目次はこちら。
http://www.bensey.co.jp/book/2272.html
以下は眼を通したもの。とりあえずはアジア系に片寄る。
鶴間和幸、歴史学と自然科学ー始皇帝陵の自然環境の復元
卯田宗平、中国における環境史研究の可能性―生業技術からみるミクロな人間ー環境系
上田信、生態環境史の視点による地域史の再構築―生物多様性の歴史的変化研究のための史料について
クリスチャン・ダニエルズ、雲南地域住民の天然資源保護・管理―十八世紀後半~19世紀前半の元江流域・メコン河上流域を事例として
石川博樹、偽バナナは消えたのか―北部エチオピアの栽培植物をめぐる歴史学的考察
海老澤衷、棚田と水資源を活用した楠木正成
高橋 学、環境史からみた中世の開始と終焉
北條勝貴、神仏習合と自然環境―言説・心性・実体
それぞれの切り口がおもしろいのであとで精読することにしたい。
新収 景教与景教碑 ほか ― 2010/10/07 22:26
路遠(著)『景教与景教碑』西安出版社、2009年5月。
張小貴(著)『中古華化祆教考述』文物出版社、2010年3月。
前者はやや概説的ではあるが、それなりに網羅されている範囲が広くて便利。
後者は祆教、ゾロアスター教研究の最新の研究書。きっちり対象をしぼって分析しているようである。ざっと見ただけだが、欧米の基本文献もよみこまれているようである。
締め切りの迫った書き物が多いので、なかなか時間が無くて、購入した本やいただいた抜き刷りが山積み。
張小貴(著)『中古華化祆教考述』文物出版社、2010年3月。
前者はやや概説的ではあるが、それなりに網羅されている範囲が広くて便利。
後者は祆教、ゾロアスター教研究の最新の研究書。きっちり対象をしぼって分析しているようである。ざっと見ただけだが、欧米の基本文献もよみこまれているようである。
締め切りの迫った書き物が多いので、なかなか時間が無くて、購入した本やいただいた抜き刷りが山積み。
新収 シルクロードの宗教 ― 2010/09/03 22:50
Richard C. Foltz(著)常塚聴(訳)『シルクロードの宗教 ― 古代から15世紀までの通商と文化交流』教文館、2003年11月。
以前どこかで書名をみたかもしれないが、遅ればせながら、先日、はじめて手にとった。「内陸アジア古代中世宗教入門―欧米における研究を中心に―」と考えると、とてもわかりやすくて便利な本である。
「帯」は内容の要約なのだろうが、具体性を欠きすぎ。これでは専門家も素人もなかなか手に取ろうとおもわないのではないかと思う。目次がWeb上に無いようなので入力。
第1章 シルクロードと旅人たち
第2章 古代ユーラシアにおける宗教と交易
第3章 仏教とシルクロード
第4章 異端者の隠れ家
第5章 シルクロードのイスラム化
第6章 キリスト教世界の誤算
第7章 もはや「るつぼ」ではない
ただこの目次は抽象的。しかし、キーワードをあげると、ソグド人、ゾロアスター教、ユダヤ教、パルティア、チベット、イラン、ネストリウス派、マニ教、イスラム、モンゴル人、という感じである。地理的にも時間的にも扱う範囲が広いので、細かいことが書かれているわけではないが、注と参考文献目録、索引をつかえば、奥へ奥へと入っていけそうなのが、この本の長所におもわれる。
以前どこかで書名をみたかもしれないが、遅ればせながら、先日、はじめて手にとった。「内陸アジア古代中世宗教入門―欧米における研究を中心に―」と考えると、とてもわかりやすくて便利な本である。
「帯」は内容の要約なのだろうが、具体性を欠きすぎ。これでは専門家も素人もなかなか手に取ろうとおもわないのではないかと思う。目次がWeb上に無いようなので入力。
第1章 シルクロードと旅人たち
第2章 古代ユーラシアにおける宗教と交易
第3章 仏教とシルクロード
第4章 異端者の隠れ家
第5章 シルクロードのイスラム化
第6章 キリスト教世界の誤算
第7章 もはや「るつぼ」ではない
ただこの目次は抽象的。しかし、キーワードをあげると、ソグド人、ゾロアスター教、ユダヤ教、パルティア、チベット、イラン、ネストリウス派、マニ教、イスラム、モンゴル人、という感じである。地理的にも時間的にも扱う範囲が広いので、細かいことが書かれているわけではないが、注と参考文献目録、索引をつかえば、奥へ奥へと入っていけそうなのが、この本の長所におもわれる。
拝受 An Analysis of the Term rkya in the Context of the Social System of the Old Tibetan Empire etc. ― 2010/09/03 00:57
IWAO Kazushi,An Analysis of the Term rkya in the Context of the Social System of the Old Tibetan Empire,The Memoirs of the Toyo Bunko,67,2009
岩尾さんからいただいた。ありがとうございました。『東方学』第113号に掲載された「キャ制(rkya)の研究序説―古代チベット帝国の社会制度」の英語版にあたる。敦煌チベット語文献にみられる古代チベット語のrkyaについて、これまでの説を退け、税制における土地単位に関わる言葉であるとする。
福島恵、罽賓李氏一族攷-シルクロードのバクトリア商人、『史学雑誌』第119編第2号、2010年2月。
福島さんからいただいた。ありがとうございました。以前、掲載誌の紹介で言及している。ソグド人の東方進出にバクトリア人のはたした役割の重要性を説く。
http://iwamoto.asablo.jp/blog/2010/03/10/4936528
岩尾さんからいただいた。ありがとうございました。『東方学』第113号に掲載された「キャ制(rkya)の研究序説―古代チベット帝国の社会制度」の英語版にあたる。敦煌チベット語文献にみられる古代チベット語のrkyaについて、これまでの説を退け、税制における土地単位に関わる言葉であるとする。
福島恵、罽賓李氏一族攷-シルクロードのバクトリア商人、『史学雑誌』第119編第2号、2010年2月。
福島さんからいただいた。ありがとうございました。以前、掲載誌の紹介で言及している。ソグド人の東方進出にバクトリア人のはたした役割の重要性を説く。
http://iwamoto.asablo.jp/blog/2010/03/10/4936528